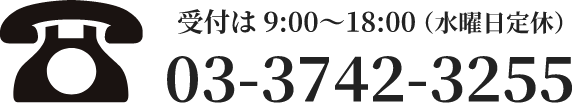2020年1月27日
日産が誇る名車「ブルーバード」の初代モデルに迫る
第二次世界大戦が終戦し、初の戦後設計となったのが「ダットサン・ブルーバード」。
日産が1959年に発表したモデルで、長い間ファンを魅了してきました。残念ながら2001年で生産終了となっており、現在ではブルーバードの名は消滅しています。
そんなブルバードは、日産初の本格小型乗用車が始まり。さまざまな技術や話題性を取り入れたモデルで、多くの魅力が詰まった一台です。
今回は日産自動車の中でも高い人気を誇る、ブルーバードの初代モデルにフォーカスし、その魅力に迫ります。
目次
1 ブルーバードの概要
日産が提供していたブルーバードは、昭和の時代に一世風靡したロングセラーシリーズ。車名の由来は童話「青い鳥」にちなんだもので、幸福を象徴するブルーバードから名付けられたそうです。
ダットサンセダンの後継車として開発されたモデルで、初代が登場したのは1959年に登場。その後10世代に渡り2001年まで生産され、多くのファンを魅了した一台です。
かつて日産自動車はダットサン系とプリンス系に分類され、ブルーバードはダットサン系の主力モデルでした。ダットサンは日産が1986年まで製造しており、商標としても扱われていたので車名などにも使用されています。ブルーバード以前の主力モデルはダットサン・トラックなどが有名です。
ブルーバードの車名もダットサン・ブルーバードが正式名称ですが、1983年に発表された7代目ブルーバードから日産・ブルーバードに車名を変更しております。
今回フォーカスしている初代ブルーバード以外にも人気モデルがあり、2代目以降に設定されたスポーツモデル「SSS」グレードや、「サメブル」の愛称で親しまれている4代目ブルーバードなどがあります。
また一部のモデルはモータースポーツに参戦し、数々の好成績を収めるスポーツカーとしての一面も垣間見えるシリーズです。現在では車好きの間でプレミア価格がつくことも少なくありません。
2 初代ブルーバードの特徴

1959年に登場した初代ブルーバードのキャッチコピーは「幸せを運ぶ青い鳥」。1963年まで提供されたモデルで、生産台数は約21万台を記録しています。「柿の種」の愛称がついていることでも知られている一台です。
ここでは初代ブルーバードの特徴についてお伝えします。
2-1 テールランプが特徴的
初代ブルーバードはセミモノコック形式を採用し、イギリス車やアメリカ車のテイストを感じさせるスタイリングデザイン。
主要部品はダットサン・トラックと共用しており、セミモノコックボディやラダーフレームを低床式にすることで、軽量化や剛性アップが図られていました。フロントサスペンションは独立懸架を採用し、乗り心地と走行性能を確保した一台です。
搭載エンジンは、先代のダットサンセダンを踏襲。2種類のエンジンが用意されており、どちらも水冷直列4気筒OHV。排気量988ccと1189ccに分類されていました。
初代ブルーバードのボディデザインを手掛けたのは、工業デザイナーとして有名な佐藤章蔵氏によるもの。リヤに装備されるテールランプの形が印象的で、お菓子の柿の種に似ていたことから「柿の種」と呼ばれることも。
2代目以降はデザイナーが変更されたので、特徴的なテールランプは初代にしか見られないデザインです。
2-2 女性目線で嬉しいファンシーデラックス
発売当初のボディタイプは、3ボックススタイルの4ドアセダンのみ。
その後、マイナーチェンジにより日本初のエステートワゴンを追加。さらに1961年には、こちらも国内初の女性仕様車「ファンシーデラックス」を発表。
これは女性向けの特別装備を施したモデルで、ボディカラーであれば見た目が映えるパステルカラーをラインナップ。
その他にもハイヒールでも操作しやすいよう、スリッパー型アクセルペダルの採用や、ハイヒールスタンド。
または化粧品入れと鏡の付いたサンバイザーや化粧用ライト、傘立てやカーテンレール、オルゴール付きウィンカーなど当時としては画期的なモデルバリエーションも特徴の一つです。
多くのファンに愛された初代ブルーバード
日産が提供するモデルの中でも高い人気を誇るブルーバード。今回はそんな人気シリーズの中でも初代ブルーバードにフォーカスし、概要や魅力などについてお伝えしました。
他の車種には見られない特徴的なボディデザインや、女性仕様車の発表など初代ブルーバードには、日産の技術力やこだわりが光る一台です。
日産が誇る名車「ブルーバード」を体験してみてはいかがでしょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。