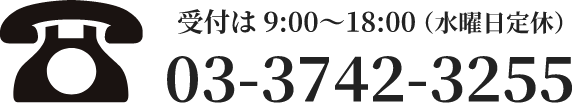2025年4月7日
トヨタ「カリーナ」31年の歴史|時代と共に変化を続けた名車の変遷
1970年、高度経済成長期の後期に登場したトヨタ「カリーナ」は、高速道路網の拡大が進む日本の道路事情を見据えた高性能スポーティセダンとして誕生しました。
車名は、りゅうこつ座を意味する英単語「Carina」に由来しています。そんなカリーナの開発背景にあるのが、モータリゼーションの本格化です。
マイカーブームにより一家に一台車を持つことが当たり前となった当時、ユーザーの多様なニーズに応えるべく、自動車メーカーには幅広いラインナップが求められていました。
小型車市場の重要性を早くから見抜いていたトヨタは、1967年にカリーナと「セリカ」の同時開発に着手。
落ち着いた印象のファミリーセダン「コロナ」や、日本版スペシャルティカーとして開発が進められた兄弟車のセリカに対し、カリーナは特に若者をターゲットとしたモデルとして位置づけられました。
そのためカリーナでは、洗練されたスタイルやスポーツ感覚を味わえる高性能、そして低価格を条件に開発が進められました。これらを両立させることで、若者の心を掴む魅力的なモデルを目指したのです。
今回は、高速走行時代の幕開けとともに誕生したカリーナは、7世代にわたって進化を続け、日本の自動車史に確かな足跡を残していくことになります。
目次
1 初代 A1/3型

1970年12月、2ドアと4ドアセダンのボディ形状でデビューした初代モデルは、コロナとほぼ同等のサイズながら、丸形4灯式ヘッドランプの内外を分けた特徴的なフロントマスクと、縦長のリアコンビネーションランプを備えた独自のスタイリングで若者の心を掴みました。
千葉真一を起用したテレビCMの効果もあり、初代カリーナは大ヒット。中・後期型では「足のいいやつ」というキャッチフレーズで親しまれ、当時としては長い7年間にわたって販売が続けられました。
スポーツ性能を重視したカリーナは、1971年4月、セリカGTと同じ2T-G型1600DOHCエンジンを搭載した2ドアセダン1600GTをラインナップに追加。三國工業製のソレックスキャブレターを2連装し、最高出力115PSという当時としては高性能なスペックを誇りました。
1972年8月のマイナーチェンジでは、コラムシフトが廃止され内外装の意匠が変更されるとともに、米国の法規改正に対応した安全・環境対策を実施。
全車にチャコールキャニスター(燃料蒸発ガス排出抑止装置)を装備し、ガソリンタンクをトランク床面下から後部座席背面に移設するなどの改良が施されました。
1972年12月には、単なるセダンの2枚ドア版ではない、ボディパネルを一新した2ドアハードトップがラインナップに追加されました。外観はセダンとはまったく異なるデザインに仕上げられ、1600シリーズ全車にフロントディスクブレーキを装備するなど、スポーツモデルとしての存在感を強めています。
1974年1月のマイナーチェンジでは、フロントグリルがハードトップと同様のものに変更され、ラインナップも1400スーパーデラックスと2000シリーズが追加されるなど充実。
1975年10月のマイナーチェンジでは「BIGカリーナ」のキャッチコピーの通り、全長・全幅・ホイールベース・トレッドがそれぞれ拡大し、内装も大幅に変更されました。
1975年12月にはバンシリーズが追加されたのもポイントです。
この時期、排出ガス規制への対応も進み、昭和50年、51年排出ガス規制に適合するモデルが次々と投入されました。1976年から1977年にかけては、TTC-L/Vモデルの追加や新1800シリーズの発売など、常に時代のニーズに応じた進化を続けました。
初代カリーナは、1977年8月に販売が終了するまでの7年間で累計71万5,680台が新車登録されるヒットを記録し、2代目へとバトンを繋ぎます。
2 2代目 A4型

1977年8月にデビューした2代目カリーナのボディは、先代同様に2ドア・4ドアセダン、2ドアハードトップ、そして5ドアバンの4タイプがラインナップされました。
なお、2ドアセダンと2ドアハードトップは、2代目をもって姿を消すことになります。
デザイン面では、初代のスタイリングに変更が加えられ、より直線基調のモダンなデザインを採用。特に4ドアセダンは箱型のノッチバックとなり、欧州セダンを思わせる洗練されたスタイルに進化しました。
そして、2代目のパワートレインにおける大きなテーマとなったのは、時代の変化を象徴する排出ガス規制への対応です。
1977年11月には、MT車の3T-Uエンジンが昭和53年排出ガス規制に適合した13T-Uへと変更。翌年5月にはGTとバンを除く1.6リッター車に3速AT車が追加され、1.8リッターの3速AT車も13T-U型エンジンに移行します。
さらに、1600GTの2T-GEU型エンジンも昭和53年排出ガス規制に適合し、110PSから115PSに出力が向上されました。
1978年9月には3T-EU型1.8リッター直列4気筒OHVエンジンを搭載するST・SR-EFIモデルがラインナップに追加。同時に2000GTの18R-GU型エンジンはEFI(電子制御燃料噴射装置)化により18R-GEU型へと進化しました。
1979年8月のマイナーチェンジでは、バンを除く全モデルのヘッドライトが丸形4灯から角形4灯ライトへと変更。併せてリヤのナンバープレート位置も変更されたことにより、モダンなスタイルへと進化しました。
3T-EU型エンジンに4速ATが追加され、2ドアセダンのスーパーデラックスおよびバンの1.4リッターが廃止されたのもポイントです。1.6リッターのバンは、12T-J型エンジンに変更され、AT車が追加されました。
1980年1月には、セダンの姉妹車となるセリカ・カムリが登場。両車はともに「セリカのセダンタイプ」という位置づけでしたが、カムリはセリカと同じくカローラ店で、カリーナはトヨタ店での取り扱いという販売チャネルの棲み分けがなされました。
このように、販売期間を通して排出ガス規制への対応が課題となっていた2代目カリーナは、1981年9月に販売を終了するまでの約4年間で累計60万9,701台が新車登録されました。
3 3代目 A6型

1981年9月にデビューした3代目は、歴代の中でも最後の後輪駆動(FR)モデルとされており、カリーナの転換点とも言えるモデルです。
3代目からはシャーシをコロナと共用化し、経済性と効率性を高めながらも、1800SEにはパワーウインドウを設定するなど装備面での充実も図られました。
カリーナの象徴とも言えるCMも継続され、おなじみの千葉真一に加えて岸本加世子が起用されたことでも話題を集めました。
ボディバリエーションでは、1982年2月にカリーナ初となる5ドアワゴン「サーフ」が追加され、ラインナップが拡充。
さらに、セダンとバンには1C型1.8リッターOHCディーゼルエンジンが設定されました。
翌1983年5月には1500SEが、さらにその翌月には女性ユーザーを意識した1500JEUNE(ジュン)が追加されるなど、多様なニーズに応える戦略が展開されたのも特徴的です。
そんな3代目カリーナの最大の特徴は、1982年10月に追加された革新的なパワーユニット。日本初となる3T-GTEU型1.8リッターDOHCターボエンジンを搭載したGT-T/TRの登場です。
「鬼に金棒、ツインカムにターボ」というキャッチコピーが示す通り、ターボチャージャーによる過給技術とDOHC機構を組み合わせた先進的なエンジンは、カリーナのスポーティなイメージをさらに強化しました。
それに伴い、コロナやセリカと同様に18R-GEU型エンジン搭載の2000GTは役目を終えました。
1983年5月のマイナーチェンジでは、横スリット線の本数が増えた新デザインのフロントグリルやテールライトデザインの変更など外観の刷新が行われ、実用面でもドアミラーが設定されました。
さらに1600GTのエンジンは2T-GEU型から、1.6リッターDOHC16バルブの4A-GEU型エンジンへと変更され、先代から引き継がれていた3T-EU型エンジンは姿を消しました。
1984年5月には、4代目のFF(前輪駆動)4ドアセダンが追加され、それに伴ってSEとSTのグレードが廃止。翌1985年8月には大幅な車種整理が行われ、1800ツインカムターボの廃止、1600GTのFFセダンへの移行、2000GT系グレードのFF化と2000GT-Rとしての復活など、駆動方式のFF化が大きく進みました。
カリーナでは、4代目のセダンと3代目を併売しつつ、徐々に車種を追加・交代する方法がとられました。
そして、これまでクーペとして親しまれてきたモデルも、FFの4ドアハードトップとして新たに生まれ変わり、名称も「カリーナED」へと変更。
こうして3代目カリーナは1988年5月にFRセダン、サーフ、バンの販売を終了し、FRからFFへと移行する過渡期のモデルとしての役目を終えました。
4代目が登場した1984年5月時点までの約4年間で累計29万9,080台が新車登録されました。
4 4代目 T15/16型
1984年5月に4ドアセダンから登場した4代目カリーナが持つ最大の特徴は、コロナと共有するプラットフォームを採用し、歴代カリーナで初めて横置きエンジンの前輪駆動(FF)方式を全面採用した点にあります。
また「足のいいやつ」のキャッチコピーが使われたのが最後というのも、4代目の特徴と言えるでしょう。
外観デザインは先代の雰囲気を踏襲しながらも、異型2灯式ヘッドライトを採用するなど、3代目よりもさらにモダンで洗練された印象に仕上げられました。
興味深いのは、トヨタが採用した移行戦略。
前出の通り、いきなり全てのラインナップをFFに移行するのではなく、4代目セダンと3代目FRモデルを併売しながら、徐々に車種を追加・交代する方法をとりました。
そのため、4代目は4ドアセダンのみがラインナップされ、クーペ、ワゴン、バンに関しては3代目が継続販売されるという棲み分けがなされました。
これにより、ユーザーの選択肢を広げつつ、スムーズな世代交代を実現したのです。
そんな4代目カリーナのパワートレインでは、1.8リッターエンジンが電子制御セントラルインジェクション(Ci)化され、排気量のラインナップも拡充。
2リッターのディーゼル車が追加されたほか、4A-ELU型1.6リッターEFIと3A-LU型1.5リッターキャブレターエンジンも用意されました。
特筆すべきは、1600SGに限り、日本初のリーンバーンエンジンが搭載されたこと。燃費と排出ガス性能の両立を目指した先進技術は、その後のトヨタエンジン開発の方向性を示すものとなりました。
1985年8月には、1600GT/GT-Rと2000GT-Rが追加され、スポーティモデルのラインナップが充実。それぞれ1.6リッターの4A-GELUと、2リッターの3S-GELUエンジンが搭載されました。
注目すべきは3S-GELUエンジンが採用された点。3S-GE系のエンジンがカリーナに搭載されたのは、4代目が最初で最後となりました。
3代目との併売により市場のニーズに応えた4代目カリーナは、1988年5月に販売を終了するまでの約4年間で、累計39万3,526台が新車登録される成功を収めました。
FF化という大きな転換点を乗り越えた4代目は、新たな時代のカリーナとしての地位を確立したモデルと言えるでしょう。
5 5代目 T17型

出典元: Walter Eric Sy / Shutterstock.com
1988年5月にデビューした5代目カリーナは、時代の流れを象徴するように丸みを帯びた滑らかなスタイリングへと大きく変貌を遂げました。
この変化は単に外観だけではなく、ブランドイメージにも及び、長年親しまれてきたキャッチコピー「足のいいやつ」から「いつもあたらしいふたりに。ときめきのカリーナ」へと変更されたことも大きな特徴です。
5代目ではサーフやバンもフルモデルチェンジが行われ、前代からの移行期間を経て、ついに全車種が前輪駆動(FF)となりました。
パワーユニットのラインナップも充実し、1.8リッターの4S-Fi型、1.6リッターの4A-GE型と4A-FE型、1.5リッターの5A-F型、そして2リッターディーゼルの2C型が用意されました。
バンには、1.5リッターの3E型とディーゼルの2C型が設定され、多様なニーズに対応しています。
1988年12月には、セダンに1.6リッター4A-FE型エンジンを搭載したセンターデフ方式フルタイム4WD車が追加されました。
さらに1989年8月には、スポーティグレードのGリミテッドに搭載される4A-GE型エンジンが高圧縮ハイオクガソリン仕様となり、出力は140PSまでアップ。
1990年5月のマイナーチェンジでは、外観面でフロントグリルが変更され、リアコンビネーションランプが3分割から2分割へと変更されました。
技術面での進化も目覚ましく、ガソリン車が全車EFI化され、1.8リッターには4S-FE型、1.5リッターには5A-FE型エンジンが新たに搭載されたのもポイントです。
FF車用の1.6リッターエンジンは、ハイカム・ハイパワー仕様の4A-FHE型へと進化し、出力が105PSから110PSへと向上。一方、4WD車には引き続き4A-FE型が採用されました。
安全性向上への取り組みも進み、このマイナーチェンジでは運転席エアバッグがオプション設定されるようになりました。
5代目カリーナは1992年7月にセダン、バン、ワゴンの生産を終了し、その翌月には6代目と入れ替わる形で販売が終了。なお、バンとワゴンについては、3か月後に登場した「カルディナ」がその後継車となります。
こうして丸みを帯びた洗練されたデザインと多彩なラインナップで時代の要請に応えた5代目カリーナは、約4年間の販売期間中に累計45万3,103台が新車登録されるという成功を収めました。
6 6代目 T19型
1992年8月に「丘の上のカリーナ」というキャッチコピーを掲げてデビューした6代目カリーナは、先代から大きな変革を遂げました。
ボディサイズが大型化され、ラインナップは4ドアセダンのみとシンプル化されたことが特徴です。
パワーユニットは、1.8リッターの4S-FE型、1.5リッターの5A-FE型、2リッターディーゼルの2C型に加え、環境性能を重視したリーンバーンエンジンの4A-FE型が設定されました。
当時、リーンバーンエンジンを搭載した車両というと、快適装備を最小限に抑えた仕様や、5速MTのみの設定など、いわゆる営業車や競技用ベース仕様が一般的でした。
しかしながら、6代目カリーナはリーンバーンエンジン搭載モデルでありながら充実した快適装備を備え、4速ATも選択できるという先進的なアプローチを採用しています。
そんな6代目カリーナの最も注目すべき特徴は、歴代カリーナの中で唯一スポーツツインカムエンジンを搭載したグレードが設定されていなかったということ。
これまで高性能グレードの象徴的存在だった4A-GE型エンジン搭載のスポーツモデルは姿を消し、4WD車のエンジンも1.6リッター4A-FE型から2リッター3S-FE型へと変更されました。
こうした方向性の変化により、同じトヨタ店で販売されていたコロナとの差別化が曖昧になってしまい、販売は低迷することとなります。
しかしながら、1.5リッターエンジンをラインナップに含めたことで、競合メーカーの同クラスと比較して廉価なモデルが存在したため、コストパフォーマンスを重視する層からは一定の評価を得ていました。
1994年8月のマイナーチェンジでは、デザインの一部が変更されるとともに、1.8リッターエンジンが4S-FE型から、さらに軽量な7A-FE型リーンバーンエンジンへと変更されました。これにより、さらなる燃費性能の向上が図られています。
このように、スポーティさよりも環境性能や経済性を重視した方向性へと舵を切った6代目カリーナは、1996年8月に販売が終了するまでの約4年間の累計新車登録は23万7,458台にとどまりました。
先代までの販売台数から大きく販売台数を減少させており、自動車市場のニーズの多様化が進む中、カリーナというモデルの立ち位置を再考させるきっかけとなったモデルと言えるでしょう。
7 7代目 T21型

出典元: Aleksandr Kondratov / Shutterstock.com
1996年8月7日にデビューした7代目カリーナは、先代の路線を引き継ぎ4ドアセダンのみの国内専用モデルとして登場しました。
基本プラットフォームは先代から継承され、T210系コロナプレミオや初代カルディナ後期型と共通のフロントドアパネルやインストルメントパネルを採用しています。
注目すべきは、この7代目からスポーツグレードGTが復活したこと。AE111型カローラレビン/スプリンタートレノと同じ165PSを発揮する1.6リッターの4A-GE型エンジンとC56型5速MTが搭載されました。
その他のパワーユニットは1.8Lの7A-FE型リーンバーン、1.5リッターの5A-FE型ハイメカツインカム、2リッターの2C-TE型ディーゼルターボを継承し、1.6リッターの4A-FE型リーンバーンは姿を消しています。
安全面では、全車に前後スタビライザーを標準装備して走行安定性を向上。トヨタの衝突安全ボディー「GOA」にABS、エアバッグも全車標準装備とし、安全装備を充実させました。
1997年11月には、ドアミラー形状の変更に加え、ビジネス仕様のEパッケージが追加されます。
このEパッケージでは助手席エアバッグやリアスタビライザー、ステアリングチルト機構など多くの装備が省かれ、ホイールも14インチ5穴から13インチ4穴へとダウンサイズ。ブレーキサイズも13インチに下げられ、コストパフォーマンスを重視した仕様となりました。
1998年8月のマイナーチェンジでは、外観デザインが大きく進化します。ヘッドランプはガラス製からプラスチック製へと変更され、内部デザインも刷新。リアコンビネーションランプも拡大され、リアバンパーフィラーは小型化されました。
また、従来別塗装だったバンパー上部とサイドモールがボディ同色となり、フロントグリルも下側に拡大されるなど、前面部のデザインが一新されています。
GTグレードではフロントグリルにGTのエンブレムが配され、ヘッドランプとフロントクリアランスランプのリフレクターには一部ブラックアウト処理が施されるなど、グレード間の差別化も明確になりました。
機能面では、GTのMT仕様車にAE111型後期カローラレビン・スプリンタートレノと共通のC160型トランスミッションが採用され、5速から6速MTに変更。前輪ブレーキは片持ち1ポットから2ポットキャリパーへと強化され、ディスクローター径も拡大。それに伴いホイール径も15インチへとサイズアップしました。
ディーゼルエンジンは2.0リッターの2C-TE型から2.2リッターの3C-TE型へと排気量アップ。安全面では、リアバルクヘッド補強材とリアサスペンションロアアーム支点を連結する補強材が追加され、リアシート中央席にもヘッドレストが装備されるなど、衝突安全性もさらに向上しています。
7代目カリーナはGTグレードが復活し、経済性や安全性を重視した仕様で奮闘するも、ピーク時の勢いを取り戻すことは叶わず、2001年12月に販売終了するまでの約6年間の新車登録台数は累計27万3,970台。
後継車アリオンの登場により31年の歴史に幕を閉じることとなりました。
セリカの兄弟車「カリーナ」7代31年の変遷
若者向けの高性能セダンとして1970年に初代が誕生したカリーナはその後、31年という長い歴史の中で7世代にわたる進化を遂げました。
セリカと同時開発されたカリーナは「足のいいやつ」というキャッチコピーと千葉真一を起用したCMで一世を風靡し、初代モデルだけで71万台以上を販売する大ヒットを記録しました。
そんなカリーナの歴史は日本の自動車産業の変遷そのものを映し出しています。排出ガス規制への対応、FRからFFへの移行、スポーツモデルから環境・経済性重視への方向転換など、時代の波を敏感に捉えた進化を続けてきました。
特筆すべきは3代目に登場した日本初の1.8リッターDOHCターボエンジン搭載車や、4代目で採用された日本初のリーンバーンエンジンなど、技術的にも最新の技術を取り入れていた点です。
5代目では丸みを帯びたデザインへと大きく変更。6代目で唯一スポーツモデルが廃止されたことで、販売台数は大きく減少。
最終となる7代目ではGTグレードが復活し、安全装備を充実させるも回復には至らず、2001年12月、31年の歴史に幕を閉じ、後続車のアリオンへとバトンを繋ぎます。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。