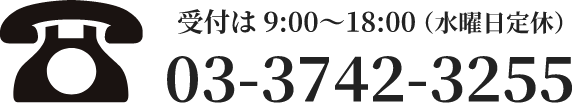2025年4月25日
オービスとは?種類から光る速度、罰金や点数について
オービスは、車のスピード違反を取り締まることや、交通事故・違反を抑止し、安全運転を促すことを目的に設置された装置です。
少し制限速度をオーバーして走行している際などに「オービスが光ったかも」と、心配になった経験のあるドライバーも少なくないはず。
本記事では、オービスの概要から仕組み、種類などの基本情報はもちろんのこと、光らせてしまった場合の処理・光らせないための対策までお伝えします。
目次
1 そもそもオービスとは?

オービスとは、走行する車両の速度を自動的に測定し、制限速度を超過した違反車両を検知すると、カメラで撮影・記録する速度違反自動取締装置です。
道路を走行する車両の速度を自動的に計測し、制限速度を超えていた場合はカメラが作動してナンバープレートと運転者の顔を撮影します。
ラテン語で眼を意味する「オービス(Orbis)」は、実はアメリカのバージニア州アーリントンに本社を置く世界最大の航空宇宙機器開発製造会社「ボーイング社」の登録商標です。
そのため、厳密にはオービスは同社製の機器のみを指しますが、日本国内では速度違反自動取締装置全般を表す言葉として使われています。
そんなオービスが日本の道路で初めて設置されたのは1973年のことで、警視庁が首都高速道路に導入したのが始まりです。その後、現在のように交通安全対策として全国の道路に広がっていきました。
オービスには固定式や可搬式など、様々な種類がありますが、いずれも速度センサーとカメラを組み合わせた仕組みで、違反車両を検知すると自動的にナンバープレートとドライバーの顔を撮影します。
交通安全の観点から、オービスの存在は事故防止や速度違反の抑止への効果が認められており、設置場所の周辺では速度違反が減少し、事故件数も低下する傾向にあります。
1-1 オービスが反応する速度
オービスが何キロオーバーで作動するかについては、正式には公表されていません。
しかしながら、速度違反でオービスに撮影された方の体験談などから、ある程度の目安に関しては推測されています。
一般道でオービスが反応するのは、制限速度から30km/h程度の速度超過が認められた場合です。ただし、住宅地などの生活道路に設置された移動式オービスの場合は、15km/h程度の超過でも反応することがあります。
一方、高速道路の場合は、制限速度から約40km/hの速度を超過した際に作動します。
かつては200km/h超ではオービスの性能を超えて測定できないという噂もありましたが、現在の高性能なオービスにはそのような限界はなく、高速走行時でも記録されるようになっています。
1-2 オービスが反応した際の光り方や明るさについて
オービスがスピード違反に反応すると、フラッシュが光ります。オービスが発するこのフラッシュには、運転者への通知という重要な役割があります。
そのため、昼間でも夜間でも、通常の運転をしていれば認識できる強く明るい光となっています。ただし、一部の小型可搬式オービスなどでは、比較的光が弱くわかりにくい場合もあるようです。
違反をドライバーに自覚させることで、切符が届いた際の手続きをスムーズにするという側面もあるようです。
そして、一般的にはオービスは赤く光ると言われますが、実際はそれだけではありません。
従来の固定式オービスの多くは赤いフラッシュを発していましたが、最近では白色に発光するタイプも徐々に増えています。加えてオレンジ色で発光する機種もあり、色は統一されていません。
実はこの色の違いには理由があり、白黒で撮影する機種は赤く発光し、カラーで撮影する機種は白く発光する傾向があるようです。
技術の進化に伴い、今後は白い光のオービスが主流になっていくという見解も見受けられます。
1-3 オービスが光らない場合
一般的にオービスは速度違反を検知するとフラッシュが光ります。
しかしながら、中には制限速度を超えて走行したのにも関わらず、オービスが光らないケースも少なくありません。
そのような場合に考えられるのが、以下のようなケースです。
- ダミーのオービスだった場合
- オービス以外のシステムだった場合
- スピードメーターの誤差
まず考えられるのがダミーオービスの存在。
場所によっては、ドライバーに速度を落とさせる心理的効果を狙って、実際には作動しないダミーのオービスが設置されることがあります。
外見からは本物と見分けがつきませんが、ダミーには撮影機能がないため、当然光ることもありません。
次に考えられるのが、NシステムやTシステム、走行中計量システム(WIM)、トラフィックカウンター(交通量調査)などのオービス以外のシステムだった場合です。
これらのカメラはオービスとはそもそもの目的が異なるため、形が似ていてもオービスのように光ることはありません。
また、車両のスピードメーターの誤差もおさえておきたい要因です。
多くの車では、実際の速度よりもスピードメーターの表示が数キロ高めに設定されています。そのため、メーター上では違反速度に達している場合でも、実際の走行速度は違反の基準には達していなかったという可能性も考えられます。
そして、基本的にオービスは、最も速度の高い車両を優先して撮影します。そのため、複数の車が同時に違反速度で走行していた場合であれば、自分以外の車が撮影されていた、という可能性も考えられるでしょう。
1-4 オービスとネズミ捕りの違い
オービスとネズミ捕りの2つは、一見似ているようで実は大きく異なる仕組みです。
主な違いとして挙げられるのは、以下の2つ。
- 速度違反が言い渡されるタイミング
- 取り締まりの違反速度の基準
両者の違いとしてまず挙げられるのは「速度違反がその場で言い渡されるかどうか」ということ。
オービスでは、速度違反をした車両を自動的に検知・撮影します。そして、違反車両を検知するとフラッシュが光り、証拠写真を撮影。後日、違反者に反則金納付書が送られる仕組みです。
一方、ネズミ捕りの場合は警察官が現場で行う取締りを指します。つまり、警察官が機器を操作し、速度違反車両をその場で停止させて違反切符を切ります。
そして、取り締まりの対象となる違反速度の基準も異なるのが特徴です。
オービスは一般的にいわゆる「赤切符」となる、一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度違反が対象とされています。
一方、ネズミ捕りはそれより低い速度超過でも取締りの対象となることがあります。
どちらも交通安全を守るための重要な取締り手段ですが、オービスは24時間体制での監視による抑止効果、ネズミ捕りは警察官による柔軟な取締りと即時性が特徴だと言えるでしょう。
2 オービス設置の予告看板について

高速道路などを走行していると目にする、自動速度取締機設置区間という予告看板。
この看板はオービスの存在をドライバーに伝えるという親切心からではなく、実は重要な法的根拠に基づいて設置されているものです。
その主な理由は、撮影されるドライバーのプライバシー保護。
たとえ速度違反をしたドライバーであっても、その人や同乗者を無断で撮影することは肖像権やプライバシー権の侵害になり得ます。
最高裁判所の判例によると、オービスで撮影した写真を速度違反の証拠として採用する場合に必要とされているのが「事前告知」と「違反行為の瞬間の撮影」の2つの条件が挙げられます。
この事前告知の条件を満たすために、予告看板の設置が必須となっているのです。
固定式オービスの予告看板の場合、代表的なパターンではオービスから2km手前、1km手前、500m手前と、設置場所手前の約1〜3kmの間に少なくとも2ヶ所の看板が設置されています。
ただし、予告看板の設置に関して全国で統一されたルールは存在せず、地域によって看板の設置場所や色、サイズなどのデザイン、文言などが異なる点が特徴です。
一方、移動式オービスの場合は予告看板を設置しないケースも多く、代わりに警察のウェブサイトやSNSなどで事前に取締りを告知したり、警察官が現場で立ち会うことで事前告知の要件を満たしています。
看板を設置する場合も通常は1枚のみで、縦長の形状をしており、道路の左側路肩や歩道に設置されるのが一般的です。
3 日本で主に稼働する7種類のオービス

現在、日本の道路には主に7種類のオービスが設置されています。
本項ではそれぞれの特徴を見ていきます。
3-1 レーダー式オービス
レーダー式は最も歴史が古く、1980年代から使用されてきたオービスです。
道路上部に設置された装置からレーダーを照射して車両の速度を測定。違反があれば路肩に設置されたカメラで撮影する仕組みです。
かつてはフィルムカメラが用いられていましたが、現在はデジタル化されているものも存在します。
埼玉県と岐阜県には、それぞれ1ヶ所ずつSSSと呼ばれる新型のレーダー式オービスが設置されています。
近年では老朽化に伴い徐々にその数を減らしつつありますが、一部はダミーとして残され、交通・違反事故の抑止に寄与しています。
3-2 ループコイル式オービス
ループコイル式は、レーダー式とほぼ同時期に登場した、歴史の古い高い精度を持つオービスです。
3つの磁場を発生させるループコイルが路面に埋め込まれ、車両がそれらのコイル上を通過する時間を測定・速度を算出し、違反がある場合は路肩のカメラで撮影します。
測定装置が道路に埋め込まれているため、目視では見つけにくく、市販のレーダー探知機では検知できないのが特徴です。
最新型は赤外線搭載のデジタルカメラで24時間監視が可能です。
3-3 Hシステム
阪神高速の頭文字に因んで名付けられたHシステムは、通称「ハンペン」と呼ばれる白い四角いレーダー装置が特徴的なオービスです。
レーダー式の進化版とされ、道路上部からレーダーを照射して速度を計測。デジタルカメラで違反車両を撮影する仕組みです。
撮影されたデータは、通信回線を通じてその場で警察に送信されます。
新型のHシステムでは、レーダーの照射パターンを変えることで市販のレーダー探知機から検知されにくい特徴を持ちます。近年では製造メーカーの撤退により、設置数は減少傾向です。
3-4 LHシステム
LHシステムは現在日本で最も設置数が多く、主力とされているオービスです。
その仕組みは、路面下に埋め込まれたループコイルで速度を計測し、道路上部のデジタルカメラで撮影するという、ループコイル式(L)とHシステムを組み合わせたもの。
レーダー照射を行わないため、市販されているレーダー探知機では検知できず、正確な速度測定が可能です。
道路をまたぐ門型やF型の支柱にカメラとストロボ、パトランプなどが設置された形状をしています。最新モデルでは1台のカメラで2車線を撮影できるタイプもあり、首都高速環状線のトンネル内にも設置されています。
3-5 レーザー式オービス
レーザー式は、2018年に登場した最新式のオービスです。
レーザー光を車両に照射し、対象車を立体的に把握して速度を計測を行います。
自立型の「LPオービス」と支柱型の「LSオービス」の2種類があり、2021年12月時点ではLPオービスは大阪府阪南市に1ヶ所、LSオービスは大阪府豊中市・吹田市・枚方市に1ヶ所づつの計3ヶ所で設置されています。
レーザーを使用するため、レーザー受信に対応していないレーダー探知機では検知できないのが特徴です。
3-6 移動式オービス
移動式はその名の通り、固定式とは異なり持ち運びができるオービスです。
主に固定オービスがない一般道や高速道路のスピードが出やすい地点で使用されています。
ワンボックスカーの後部に速度計測装置とカメラを搭載し、場所を移動して取締りを行うため、どこで測定されるか予測できません。
レーザー式と新Kバンド周波数帯を使用する新型のレーダー式がありますが、現在はレーザー式が主流です。
設置時には速度取締中の看板が設置されますが、一般的なオービスの予告看板と比べて見落としやすいとされています。
3-7 新型の小型オービス
2014年頃から導入が始まった新型の小型オービスは、主にゾーン30と呼ばれる、制限速度が30km/hの市街地エリアに設置されている小型のオービスです。
生活道路の安全確保を目的としていることから、速度違反の撮影だけでなく歩行者や自転車への警告機能を備えているのがポイント。
そして、レーザーを使用して速度を測定するため、一般的なレーダー探知機では検知しにくい特徴を持ちます。さらに、予告看板が設置されない場合もあります。
4 オービスを光らせてしまったら

本項では、オービスを光らせてしまった場合の処理について、速度違反の罰金と点数と、処分の流れに分けてお伝えします。
4-1 速度違反の罰金と点数について
オービスに撮影されてしまった場合、反則金・罰金や違反点数は気になるポイントです。
一般的にオービスが反応するとされている超過速度は、以下の通り。
- 住宅地などの生活道路:15km/h程度の速度超過
- 一般道:30km/h程度の速度超過
- 高速道路:40km/h程度の速度超過
反則金・罰金や違反点数に関しては、上記のオービスが反応する超過速度の目安と、以下の表を比較してみましょう。
| 超過速度 | 点数 | 反則金(普通車) | ||
| 一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 | |
| 15~20km/h未満 | 1点 | 1万2,000円 | ||
| 20~25km/h未満 | 2点 | 1万5,000円 | ||
| 25〜30km/h未満 | 3点 | 1万8,000円 | ||
| 30~35km/h未満 | 6点 | 3点 | 6~8万円 | 2万5,000円 |
| 35~40km/h未満 | 3点 | 3万5,000円 | ||
| 40~50km/h未満 | 6点 | 裁判によって 罰金額が決定 |
||
| 50km/h~ | 12点 | 6~10万円 | ||
生活道路で移動式のオービスが反応するのは、15km/h程度からとされています。そのため、違反点数は1点から、反則金に関しては1万2,000円から、超過した速度に応じて加算されます。
一方、それ以外の場合でオービスが反応するのは、一般道で30km/h程度から、高速道路で40km/h程度からとされています。
つまり、生活道路以外でオービスが反応するのは、免許証保管証(通称:赤切符)が交付されるということです。
このような重大な違反に対しては、無免許運転や轢き逃げなどと同じく刑事処分となり、反則金ではなく刑事事件上の罰則が科せられます。
さらに、そのような重大な違反を繰り返している場合や、大幅に制限速度を超過をした場合には、裁判により懲役刑が科せられることもあることを覚えておきましょう。
4-2 処分の流れ
本項では、オービスに検知されてから一連の処分が終わるまでの流れについて、順を追ってお伝えします。
4-2-1 出頭通知書が届く
オービスに検知されてから約1週間~1ヶ月後、車の所有者宛に、違反の日時や場所、出頭すべき警察署と日時が記載された出頭通知書が届きます。
指定された日時に出頭できない場合は、警察に連絡すれば変更可能です。
4-2-2 警察署への出頭・事情聴取
指定された警察署に出頭すると、オービスで撮影された画像が提示され、事実確認が行われます。
違反を認めると超過速度に応じて交通反則告知書(青切符)または告知票・免許証保管証(赤切符)が交付されます。
生活道路の移動式を除き、一般的にオービスが反応するのは一般道で30km/h程度から、高速道路で40km/h程度からとされているため、ほとんどの場合は赤切符が交付されると考えて良いでしょう。
4-2-3 出廷通知書の到着
赤切符を交付された場合は、数日~1ヶ月ほどで裁判所から出廷通知書が届きます。
出廷通知書も出頭通知書と同じく、出廷日時と場所が記載されており、都合が合わない場合は変更が可能です。
4-2-4 簡易裁判所への出廷
指定された簡易裁判所に出廷すると、書面で審理する略式裁判に同意するかどうかの確認があり、同意すれば当日中に判決が下されます。
罰金の金額は最高で10万円とされているため、その場で支払う場合は現金を用意しておくと良いでしょう。後日、振込での支払いも可能です。
4-2-5 行政処分のための呼出通知書
裁判が終わると、警察署から行政処分のための呼出通知書が届きます。
これは罰金とは別に、免許証に関する行政処分を行うためのものです。
4-2-6 免許停止処分の手続き
通知に従って警察署に出頭し、免許停止処分の手続きを行います。
一般的にオービスが作動するとされる速度超過では6点以上の違反点数が付与されるため、免許停止処分は免れません。
4-2-7 免許停止処分者講習の受講
免許停止期間を短縮したい場合は、任意で免許停止処分者講習を受講することができます。
講習は短期・中期・長期の3つがあり、それぞれ短縮される日数や費用が異なるのが特徴です。
4-2-8 免許証の返還
免許停止期間が終了すると、免許証が返還されます。これで一連の処分の流れは終了です。
このような面倒な手続きを経験しないためにも、常に制限速度を守る習慣を身につけることが大切です。
4-3 通知が届かない場合
オービスのフラッシュが光ったにもかかわらず、数週間経っても出頭通知書が届かないケースがあります。
本項では、その理由についてお伝えします。
4-3-1 撮影に失敗していた可能性
速度違反があってもオービスの撮影自体に問題がある場合があります。
例えば、悪天候や濃霧、強い雨などによりカメラの視界が妨げられるような場合や、大型車両などの障害物によってナンバープレートや運転者の顔が隠れてしまい、特定できないような場合が考えられます。
このように、撮影した画像が証拠として採用できない場合、出頭通知書は届きません。
4-3-2 機械の故障やメンテナンス
機械である以上、オービスも故障することがあります。特に古いタイプのオービスでは、フィルム式カメラを使用しているタイプがあり、フィルム切れや機械の不具合で撮影に失敗することがあります。
しかしながら、現在ではほとんどのオービスがデジタル化されているため、フィルム切れに関しては考え難いですが、メンテナンス中や通信系統のトラブルで画像データが正しく送信されなかった場合などは、出頭通知書が届かない可能性が考えられるでしょう。
4-3-3 住所変更が反映されていない
出頭通知書は車検証に記載された住所に送られるため、引っ越しなどで住所変更手続きをしていない場合には、通知書が届かないケースがあります。
そのような場合は届かなくなるのではなく、届くのが遅れているの状態のため、いずれ前住所から転送される、もしくは戻ってきた通知書をもとに調査が行われることになります。
4-3-4 運転者の特定に時間がかかっている
レンタカーや知人の車を運転していた場合、車の所有者から実際の運転者を特定する作業が発生することから、自身が所有する車を運転していた場合よりも出頭通知書の到着に時間がかかることがあります。
会社が所有する社用車などの場合も同様で、どの社員が運転していたのかを確認しなくてはならないため、通知が遅れる場合があります。
4-3-5 ダミーのオービスの場合
一部の地域では、速度抑制効果を狙ってダミーのオービスを設置していることがあります。
それらは本物と同じ外見をしているものの機能はしていないため、フラッシュが光ったように見えても実際には撮影されていません。
ただし、通知が届かないからといって安心するのは禁物です。事務処理の都合で遅れている可能性も考えられるでしょう。
5 オービスを反応させないための対策

本項ではオービスに注意するための効果的な方法についてお伝えします。
5-1 事前にオービスの設置場所を把握する
オービスの設置場所を事前に把握しておくことは、安全運転への意識を高める上で効果的です。
固定式オービスの場合、設置場所の手前には必ず自動速度取締機設置路線などの文言が記述された予告看板が設置されています。
普段よく通る道路であれば、これらの看板の位置を覚えておくことで、オービスに備えることが可能です。
また、旅行など普段通らない道路を運転する際は、事前にインターネットでオービスの設置場所を確認しておくと安心です。
特に高速道路や主要な一般道については、オービス設置地点の情報がウェブ上で公開されているケースも多く見られるため、予めチェックしておくといいでしょう。
5-2 オービス検知アプリを活用する
スマートフォンの地図アプリやナビゲーションアプリの中には、オービスの設置場所を知らせる機能を持ったものがあります。
これらのアプリは道路状況や渋滞情報、駐車場の空き情報など、運転に役立つ様々な情報も提供しているため、普段のドライブなどでも便利に活用できるのもポイントです。
特に近年のアプリは、ユーザーからの情報提供機能を持つものも多く、移動式オービスの設置情報なども反映されることがあります。
ただし、すべての移動式オービスを網羅しているわけではないので、頼り過ぎは禁物です。
5-3 レーダー探知機の活用
オービスに備えた対策として、市販のレーダー探知機を自動車に設置する方法もあります。
レーダー探知機はオービスから発せられるレーダー波を検知して警告してくれるほか、GPS内蔵タイプを選択すると、固定式オービスの設置位置に近づくと音や光で通知を受け取れることが可能です。
しかしながら、最新式のLHシステムやレーザー式オービスなど、レーダー波を使わない方式のオービスの場合、従来のレーダー探知機では検知できないケースも少なくありません。
さらに、レーダー探知機の性能や設置場所によっては検知の精度が落ちるケースも考えられるため、完全な対策とは言い切れないでしょう。
5-4 制限速度を遵守する
オービスを光らせないための最も確実な方法は、制限速度を守ることです。
一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過をすると、オービスが作動することが多く、免許停止などの重い処分を受ける可能性があります。
下り坂では意図せずにスピードが出てしまうこともあるため、注意が必要です。オートクルーズコントロール機能があるモデルの場合、高速道路で活用するのも有効な手段と言えます。
道路を安全に利用するためにも、まずは制限速度の遵守を心がけましょう。
制限速度を遵守して安全なドライブを
オービスは単なる速度違反の取締り装置ではなく、交通事故や違反を未然に防ぎ、安全運転を促すための重要な役割を担っています。
オービスが反応する明確な速度は公表されていないものの、その目安は住宅地などの生活道路では15km/h程度の速度超過、一般道では30km/h程度の速度超過、高速道路では40km/h程度の速度超過で作動するとされています。
一般道や高速道路でオービスが反応するのは、赤切符が交付される重大な違反に該当するケースです。
このような大幅な速度超過は、制限速度を守る意思があるドライバーによる運転では起こりにくいものです。
つまり、オービスはうっかり程度の小さな違反を取り締まるためではなく、明らかに危険な速度で走行する車両を対象としているということ。
反則金や罰金の支払い、免許停止などのペナルティを避けるという点はもちろんですが、何よりも自分自身や他の道路利用者の命を守るためにも、最高速度・法定速度を守ることは極めて重要です。
一人一人が制限速度を守り、誰もが安心して利用できる環境を作る意識を持つことが最も大切なのではないでしょうか。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。