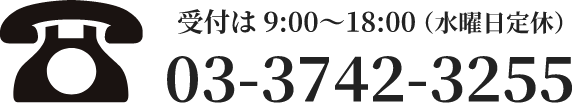2024年6月7日
車のバンパーの役割は?歴史から紐解くデザインや素材
車の前後に必ず装備されているバンパーと呼ばれるパーツ。普段あまり車を利用しない方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
そんなバンパーは車のデザインを左右する大切な要素。その形状や素材はこれまでの自動車の安全基準や、技術の進歩に影響を受けながら時代と共に変化してきました。それぞれの年代を反映する車のスタイルは、バンパーによって決定づけられていると言っても過言ではありません。
しかしながらその本質はデザインではなく、いざという時ドライバーや歩行者の安全を守る重要な役割にあります。デザインに注目が集まりがちなパーツだからこそ、その背景や役割を充分に理解することが大切と言えるでしょう。
そこで今回は車のバンパーの役割や素材、デザインの変化を交えつつその歴史を紐解きます。
目次
1 車のバンパーとはどこの部分?

そもそもバンパーとは車体に装備されている緩衝装置のこと。車体の最前・後部それぞれに装備され、軽度の衝突時に衝撃や振動を緩和しボディを守る役割を担っています。前部に装備されているものは「フロントバンパー」、後部のものは「リアバンパー」と呼ばれています。
バンパーにナンバープレートを装着するタイプのモデルも多く、グリルが一体になった形状やフォグランプを覆う形状が一般的です。
近年では自動車の安全性が高まったことから、本来の目的以外にも車のデザインの一部として扱われる傾向があります。空気抵抗を意識した形状や、分割式、エアロパーツと一体型のバンパーなど、その形状はさまざま。
バンパーは安全性を高めるだけでなく、車の表情を構成する大切なパーツと言えるでしょう。
2 バンパーの素材による違いとデザインの変遷

本来緩衝装置としての役割を持つバンパーは、1980年代までは耐久性に優れ取り外しが容易な金属製の棒状バンパーが一般的でした。高い強度を持つ金属バンパーは衝突した場合でも破損しづらく、再利用しやすいのがメリットです。しかしながら事故の際にはその堅牢さが仇となり、歩行者にダメージを与えやすいという側面もあります。
そんな金属製バンパーの中でも特に有名なのが1970年代の車に見られる大型バンパー、通称「5マイルバンパー」です。アメリカでは1972年9月に連邦自動車安全基準が改正されたことにより、車には当時の試験速度とされていた時速5マイル(約8km/h)以下で衝突した際の衝撃吸収・復元を基準としたバンパーの装着が義務化されました。その影響は欧米のメーカーだけにとどまらず、欧米仕様車を生産していた日本の自動車メーカーにまで及びます。
1980年に現在では当たり前となったエアバックが登場し車の安全性が高まったこともあってか、10年後の1982年になるとアメリカの試験速度が2.5マイルに引き下げられました。そして無骨な5マイルバンパーは、軽量なバンパーへと徐々に置き換わっていきます。
そこで登場したのが現在の主流となる樹脂製のバンパーです。金属製と比較すると割れやすく耐久性は劣るものの、形成が容易なことや軽量かつ柔軟なため軽度の衝突の場合には復元しやすいこと、事故の際に歩行者に与えるダメージが少ないなどの特徴を持ちます。
それ以降はデザイン性の高いものや空気抵抗を意識したバンパーが徐々に増え、1990年代になると自動車の大半が樹脂製のバンパーを装備するようになりました。近年の自動車に多く見られるバンパーにボディと同系色の塗装が施される、ライトが埋め込まれる、ボディと一体化するなどのデザインに重きを置く流れは、1980年代から始まったのです。
また、バンパーは日本と海外でその扱いが異なるのもポイント。日本国内ではバンパーは車のボディの一部としてみなされ、傷がついたり破損した場合には補修する場合が多く見られます。ダメージの程度によっては車検に通らないことも。一方で海外ではバンパー本来のボディを衝突から守る目的に重きを置き、傷がついてもそのままにされるケースが多いのが特徴です。
国産車と外車の違いは、実用性やデザインに対する考え方の差から生まれているところも大きいのではないでしょうか。
3 バンパーはどうやって修理するの?

前述の通り、本来自動車を守る目的で装備されているバンパーは、その多くが車体の最前・後部に突き出した形状をしています。そのため、傷つくことが多いパーツと言えるでしょう。そんなバンパーに傷をつけてしまった場合、ちょっとしたダメージや浅い擦り傷は自分でも補修できます。
作業しにくい場所の補修をする場合は、あらかじめバンパーを外して作業するのがおすすめ。車体の裏側、タイヤハウス、ボンネット内のネジやランプのコネクタなどを外し、バンパーを取り外しましょう。バンパーの取り外しを行う際には、ツメを折らないように慎重に作業してください。
そして修理前には粗目と細目のコンパウンド、スポンジもしくは拭き取り用クロスを用意しておきましょう。修理手順は以下の通り。
- 修理箇所を洗い、きれいに汚れを落とす
- 粗目のコンパウンドを使い、スポンジもしくは拭き取り用クロスで傷がある程度目立たなくなるまで円を書く様に磨く
- 細目のコンパウンドを使って仕上げをする
上記はあくまでも傷を目立たなくする方法です。傷が深い場合にはタッチペンやパテを使って補修する必要があります。
自分で補修するのに不安がある場合や傷が大きい場合には、修理・整備を得意とする業者に相談するのがおすすめです。
ヴァ・ベーネは、自社内に国土交通省の認証工場を完備。改造やメンテナンスはもちろんのこと、社外品への交換や、入手の難しい旧車のパーツまで幅広く、柔軟に対応可能です。
車に関してお困りのことがあれば、確かな技術と経験を持つヴァ・ベーネにご相談ください。
愛車に乗り続けたい方を全力でサポートします。お気軽にご相談ください。
デザインや安全性を担う車のバンパー
今回は車のバンパーの役割や、それにまつわる歴史についてお伝えしました。
本来バンパーは車体の前後に装備された緩衝装置として誕生したパーツです。1982年になるとアメリカの試験速度が引き下げられたことによって、さまざまな形状のバンパーが登場しました。近年の自動車に見られるバンパーのデザインに重きを置く流れは、1980年代から始まったと言えるでしょう。
そんなバンパーに傷をつけてしまった場合、ダメージの程度によっては車検に通らないこともあるため補修が必要です。浅い擦り傷などは比較的簡単に補修できるものの、自分で補修するのに不安がある場合や傷が大きい場合には、修理・整備を得意とする業者に相談してみましょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。