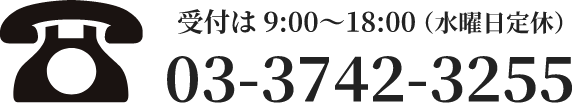2025年8月8日
スポーツと実用を両立した、ホンダ・インテグラの軌跡
ホンダ・インテグラは、1985年に誕生したスポーティコンパクトカーであり、同社が誇る高回転型エンジン技術や、卓越したハンドリング性能を一般ユーザーにも届けた象徴的なモデルです。
特に、可変バルブタイミング機構「VTEC」や高性能グレード「タイプR」といった革新的技術の実装は、国内外で大きな反響を呼びました。
インテグラは、走行性能と日常での使いやすさを両立させたパッケージで、若者からベテランドライバーまで幅広い層に支持されてきました。その魅力は単なるスペックの高さに留まらず、「人と車との一体感」を実感できる、ドライビングプレジャーそのものにあります。
また海外では、高級ブランド「Acura(アキュラ)」のラインナップとして展開。特に北米市場では「Acura Integra」「Acura RSX」として長年人気を博し、洗練された内外装と高い装備品質で、ホンダ車の上級イメージを確立しました。
今回は、ホンダが開発したインテグラにスポットを当て、初代から最新型について見ていきましょう。
目次
1 実用セダンとスポーティを融合させた「初代インテグラ」

インテグラの歴史は、1985年に「クイントインテグラ」として幕を開けました。これは、当時の5ドアハッチバックセダン「ホンダ・クイント」をベースに、より上級かつスポーティな仕様として企画されたモデルです。
開発段階では「クイントの高性能・高級版」という位置付けでしたが、実際の販売では独自の個性が際立ち、ホンダの新しいラインアップの柱となりました。
ボディバリエーションは、5ドアハッチバックと3ドアクーペからスタートし、後に4ドアセダンも追加されました。ホンダとしては、クーペとセダン、そしてハッチバックを同時展開するという、実用と趣味性を兼ねた商品構成を打ち出していた点が特徴です。
エクステリアは、当時流行していた直線基調のシャープなデザインで、洗練されたスポーツイメージを前面に押し出しています。内装面でも、デジタルメーターや高級感のあるトリム、クラスを超えた快適装備が揃えられ、当時の小型車とは一線を画す仕上がりとなっていました。
最大の特徴は、DOHC(ツインカム)1.6L ZC型エンジンの搭載です。最高出力は135ps(当時の自主規制枠内)で、軽量な車体と相まって非常に軽快な走行性能を実現していました。このZC型エンジンは、シビックSiやCR-Xにも搭載されており、ホンダが誇るスポーツコンパクト路線を象徴する存在です。
また、初代インテグラは駆動方式としてFF(前輪駆動)を採用しつつも、シャシーの設計やサスペンションの熟成により、優れたコーナリング性能を持ち合わせていました。これは後のVTEC搭載モデルやタイプRへとつながる、ホンダFFスポーツの原型といえる存在です。
2 世界初、VTECを搭載しカルト的な人気を博した「2代目インテグラ」

1989年にフルモデルチェンジされた2代目インテグラは、先代の直線的なデザインから一転し、個性的で先進的なルックスをまとって登場しました。
中でも最も印象的だったのは、当時としては異例ともいえる「丸目4灯ヘッドライト」の採用です。このデザインは賛否両論を巻き起こしながらも、インテグラの存在感を強烈に印象づける要素となりました。
シャシー性能も大幅に向上しており、ボディ剛性の強化や前後重量バランスの最適化により、操縦安定性が格段にアップ。結果として、スポーツドライビングにおける“気持ちよさ”がより明確に感じられるモデルとなっています。
2代目インテグラ最大のトピックは、ホンダが開発した世界初の可変バルブタイミング・リフト機構「VTEC(Variable Valve Timing and Lift Electronic Control)」を初めて市販車に搭載したことです。
この技術は、低回転域では燃費やトルクを重視し、高回転域では高出力・高レスポンスを実現するという、まさに“二律背反”を克服した革新でした。搭載されたB16A型エンジン(1.6L DOHC VTEC)は、自然吸気エンジンながら160psという高出力を発揮し、「高回転まで気持ちよく回るホンダエンジン」のイメージを決定づけました。
このモデルにより、「走りのホンダ」「VTEC=ホンダの代名詞」といったブランドイメージが一気に広まり、若年層を中心にカルト的な人気を博します。
2代目インテグラは、エンジンや装備によって多彩なグレード構成が展開されました。
-
XSi/RSi:B16A型VTECエンジン搭載の高性能モデル。専用サスペンションやアルミホイールなども装備
-
ZXi/RXi:1.6L SOHC仕様のベーシックグレードながら、日常使いにも最適な快適性を確保
-
4ドアハードトップ(DA8):セダンボディながらスポーティな走りと上質な内装で、上級志向ユーザーにも対応
これらのグレード展開は、インテグラの「スポーティ×実用」というコンセプトをより明確にし、幅広いユーザー層の獲得に貢献しました。
3 “走り”を追求し誕生したFFスポーツの金字塔「3代目インテグラ」

1993年に登場した3代目インテグラは、モデルチェンジを経て一層洗練されたスポーツモデルへと生まれ変わりました。外観は空力性能を意識した流麗なフォルムに刷新され、角ばった従来のイメージから一転、現代的かつダイナミックな印象を与えるデザインへと変貌しました。
型式は2ドアクーペが「DC2」、4ドアセダンが「DB8」となり、それぞれにスポーツ性能と実用性を兼ね備えた仕様が用意されました。シャシー剛性やサスペンション性能も飛躍的に向上しており、日常使いからワインディングまで高次元のドライビングフィールを実現しています。
3代目インテグラの最大の特徴は、1995年に追加された高性能グレード「インテグラ タイプR(DC2)」の存在です。このモデルは、ホンダが本気で“走り”を追求した結果生まれた、極めてストイックなFFスポーツカーです。
搭載されるB18C型エンジンは、従来のVTECユニットをベースに細部まで徹底的に鍛え直された専用品。ポート研磨や高圧縮比ピストンの採用、バランス取りの徹底など、まさに手組みエンジンといえる仕上がりで、200ps(当時の最高自主規制)を自然吸気で絞り出します。レブリミットは8,400rpmに達し、ホンダならではの高回転NAユニットの魅力を極限まで引き出しています。
タイプRは、車体にも大きな改良が施されています。スポット溶接の追加による剛性アップ、遮音材や快適装備の軽量化、専用LSD(ヘリカル式)とショートストロークシフトの搭載など、まさに“走るための装備”に特化した仕様となっていました。
この徹底ぶりは、市販FF車としては異例であり、当時から「公道を走れるレーシングカー」と称されたほどです。
DC2は2ドアクーペ、DB8は4ドアセダンですが、どちらにもタイプRの設定が存在します。DB8型のタイプRは、ファミリー層や通勤にも対応できる“実用スポーツ”としての側面を持ちつつ、DC2譲りの性能を維持しており、一部では“隠れた名車”として再評価されています。
3代目インテグラ タイプRは、国内外のレースシーンでも輝かしい実績を残しています。スーパー耐久、ジムカーナ、ワンメイクレースといったカテゴリーでの活躍を通じて、“FF最速”の称号を確固たるものにしました。
特に軽量×高剛性×高回転型NAエンジンという組み合わせは、ハンドリング重視のコースにおいては後輪駆動車をも凌駕する性能を発揮したこともあります。
4 DC5が切り拓いた、新世代FFスポーツのカタチ「4代目インテグラ」

2001年に登場した4代目インテグラは、従来の直線的かつシャープなデザインから一転し、曲線を多用した流麗なフォルムに生まれ変わりました。
ボディタイプは3ドアクーペのみで、リアハッチゲートを備えたハッチバック風のシルエットが特徴です。これによりスタイルだけでなく実用性も高められ、スポーツカーでありながら日常ユースにも適していました。
内装も大幅にアップデートされ、質感の向上と共に、メーター類やシートポジションなど、ドライバー視点での機能配置が見直されました。特にタイプRには、赤バケットシートやチタン製シフトノブ、MOMO製ステアリングなど、専用装備が投入されています。
4代目で最も大きな技術的変化は、新開発のK20A型2.0L DOHC i-VTECエンジンの搭載です。これにより、これまでのB型VTECから新世代へとパワートレインが移行しました。
i-VTECは、従来のVTEC機構に加え、可変バルブタイミング制御(VTC)を組み合わせたシステムで、全回転域においてより最適なバルブ制御を実現しています。これにより、従来よりもトルク特性が大幅に改善され、街乗りからサーキットまで幅広いシーンで扱いやすくなりました。
タイプR仕様では、K20Aエンジンは専用チューニングが施され、220psを発揮。組み合わされる6速マニュアルトランスミッションはクロスレシオで、シフトフィールも徹底的に磨かれています。
従来のDC2型までは前後ともダブルウィッシュボーン式サスペンションが採用されていましたが、DC5ではフロントがマクファーソンストラット式へと変更されました。これにより軽量化とコスト削減、整備性の向上が図られた一方で、「走り」の観点では従来より評価が分かれることとなりました。
ただし、DC5のシャシーは非常に高剛性で、専用セッティングのサスペンションやトルセンLSDの効果により、限界域での安定感やトラクション性能は非常に高水準にあります。ハンドリング特性は従来とやや異なるものの、熟成されたDC5は今なお“現代でも通用するFFスポーツ”として高い評価を受けています。
DC5型は、日本国内に加え、北米市場では「Acura RSX」の名で販売されました。特にType-Sグレードは、国内仕様のタイプRと異なるセッティングながら、高出力エンジンと上質な内装で多くのファンを獲得しています。
また、ワンメイクレースやクラブマンレースでも活躍し、カスタムベース車両としても人気が高いモデルです。チューニングパーツの豊富さやエンジンの耐久性も、DC5の魅力を支える要素となっています。
5 復活を遂げた「5代目インテグラ」の挑戦

2022年、インテグラの名が約16年ぶりに復活を遂げました。ただし、その舞台は日本ではなく北米市場。高級ブランド「Acura(アキュラ)」のラインアップとして復活した5代目は、シビック(FL型)をベースに設計され、5ドアリフトバックという新しいボディ形式で登場しました。
当モデルは、「スポーツコンパクト」というかつてのインテグラの価値を現代的に再解釈した一台です。若年層や新しい世代の自動車好きをターゲットに据えつつ、かつてのファン層にも訴求するべく、走りと実用性の両立が強く意識されています。
デザイン面では、アキュラブランド共通の“Diamond Pentagon Grille”を採用し、精悍かつプレミアム感のある顔つきに仕上げられています。リアには「INTEGRA」の文字が大胆にエンボスされ、伝統と革新の融合を感じさせるディテールが随所に盛り込まれています。
インテリアにはデジタルメーターや大型インフォテインメントスクリーンを標準装備し、Apple CarPlayやAndroid Auto、Wi-Fi接続など最新のコネクティビティ機能も完備。先進運転支援システム(ADAS)も充実しており、スポーツモデルでありながら現代のニーズに応える仕様となっています。
5代目インテグラに搭載されるエンジンは、1.5L直列4気筒VTECターボ(L15CA型)で、最高出力は200hp。これは北米仕様のシビックSiと共通のユニットであり、力強いトルクと高効率を両立しています。
トランスミッションはCVTが標準ですが、6速マニュアル仕様も選択可能。さらに、MTモデルにはレブマッチング機構(自動ブリッピング)や機械式LSDが装備され、FFスポーツとしての走りを重視した設定がなされています。
この走りを楽しめるMTモデルが復活したことは、かつてのインテグラファンにとって非常に大きなニュースとなりました。
2023年には、さらなる高性能バージョンとして「Integra Type S」が加わりました。当モデルは、FL5型シビック・タイプRと基本的な構成を共有し、K20C1型2.0Lターボエンジン(最高出力320hp)を搭載。6速MT+LSDを備え、FF最速クラスのパフォーマンスを誇ります。
外観はフェンダーの張り出しや大型リアディフューザーによりアグレッシブに仕上げられ、インテリアにはスポーツバケットシートや専用トリムが採用されるなど、細部まで専用設計が施されています。
ただし、インテグラ Type Sは日本国内では正規販売されておらず、現在のところ北米専売モデルとなっています。そのため、国内で乗る場合は並行輸入や個人輸入という手段に限られます。
インテグラが今も支持され続ける理由
ホンダ・インテグラは、単なるスポーツカーという枠に収まらない存在です。その人気の源泉は、「走り」と「実用性」のバランス、そしてホンダが追求してきた“人を楽しませる車づくり”の思想にあります。
インテグラは、ホンダが「走りの楽しさ」を真摯に追求し続けた結果として生まれ、進化を重ねてきた名車です。高性能であること、実用性を備えていること、そして何よりも“運転が楽しいこと”を一貫して提供し続けてきました。
その歴史は単なるモデルチェンジの連続ではなく、「車と人との関係性を深める」ための挑戦の軌跡でもあります。
現在も中古車市場で高い人気を保ち、そして新型での再登場を果たした今、インテグラという名前は次世代のドライバーへと確実に受け継がれています。
今後も“ホンダ・インテグラ”は、走りを愛するすべての人々の記憶と心に刻まれる存在であり続けるでしょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。