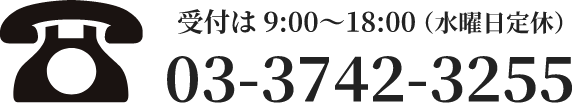2025年5月12日
日産レパードが辿った20年の軌跡
1980年から2000年までの約20年間、時代とともに姿を変えながら展開した日産の高級車「レパード」。
そんなレパードは、日産店での取扱車種のラインナップ上、ブルーバードの上級グレードの後継車種としての位置付けと、スカイライン、ローレルに続く上級車ラインナップの一角を担うべく、1980年10月に発売されたモデルです。
レパードは全4世代にわたって生産されるも、世代ごとに企画の変転が大きかったことでも知られています。
初代F30型は910型ブルーバードベースの上級2ドア/4ドアハードトップ、2代目F31型はR31型スカイラインベースの高級2ドアクーペ。
3代目JY32型は「レパードJ.フェリー」と改称され、よりパーソナルな高級4ドアセダンに、そして4代目JY33型では再び「レパード」の名に戻してセドリック/グロリアベースの高級4ドアハードトップという変遷をたどりました。
このように、レパードは世代を通して一貫したコンセプトを持ち続けることができなかったことで知られています。
しかしながらレパードでの経験は、その後のシーマやフーガ、スカイラインなどの高級パーソナルカーの開発における礎となりました。
目次
1 新世代ハイオーナーカー初代 F30型と、新高級スペシャリティカーと位置付けられた姉妹車レパードTR-X

1-1 当初は北米輸出向けとして計画されていた初代レパードF30型
1980年9月、日産の高級ハードトップとして初代レパードF30型が華々しく登場。
開発は東京都杉並区荻窪にあった旧プリンス自動車工業の拠点で行われ、当初は北米輸出向けとして計画されていました。
しかしながら、完成時期に北米市場が冷え込んでいたことから計画変更。日本国内専用車として販売されることとなりました。
そんな初代レパードは、910型ブルーバードをベースにホイールベースを延長し、L24E型直列6気筒エンジンを搭載した北米向けモデルG910型「マキシマ」の日本市場向けバージョンという位置づけ。
ブルーバードの上級グレードの後継という性格から、ブルーバードを主に取り扱う日産店での販売が主流となりました。
ボディタイプには4ドアピラードハードトップと2ドアハードトップの2種類を設定されていたのがポイント。
これには当時の運輸省が車種増加を事実上禁止していたという背景があり、ブルーバードGTの後継として認められるよう、4ドアも用意するという苦肉の策が取られたという経緯があります。
広告面では加山雄三氏をCMに起用し「パワーエリート」「自由に何を賭けるか」などの前期のキャッチコピーや、後期の「最先端は、愉快だ」「鋭く挑む、華麗なる豹」などの印象的なフレーズで高級感とスポーティさをアピール。
そして、ドラマや映画の劇中車としても多く採用されたのがポイントです。
加山氏が出演したドラマ「探偵同盟」や「愛のホットライン」「ブラックジャック」映画「帰ってきた若大将」などさまざまな作品に登場し、知名度の向上に大きく貢献しました。
初代レパードは世界初あるいは業界初となる装備を多数採用していたのも特徴の一つ。当時としては先進の燃費計やフェンダーミラーワイパーといった装備が話題を呼びました。
デザイン面では、リアウィンドウにベンドグラスを採用。さらにCピラーとリアフェンダーを面一にしない独自の手法を特徴とし、当時の国産車には見られない先進的なスタイリングが目を引きました。
エンジンは当初、直列6気筒の2リッターのL20E型と2.8リッターのL28E型、Z型直列4気筒のZ18型 1.8リッターという「技術の日産」を謳うにはやや旧式な印象は否めないラインナップでした。
当時、同クラスで後発のトヨタ ソアラには、最高出力170馬力を誇る直列6気筒DOHC 2.8リッターエンジンを搭載するグレードが存在。一方、レパードはSOHCエンジンのみで最高出力もL28E型の145馬力に留まり、性能面での劣勢は明らかでした。
この苦境を打開すべく、1984年には前年発売のフェアレディZ300ZXと同じVG30ET型 V型6気筒ターボエンジンを搭載した300ターボグランドエディションを追加。最高出力230馬力を実現し、ソアラと互角以上のパフォーマンスを獲得したものの、期待された販売増加には繋がりませんでした。
発売直後の1981年7月にはL20ET型 直列6気筒2.0Lターボエンジンも追加されたほか、1982年9月のマイナーチェンジではラジエーターグリルとテールランプのデザイン変更。AT車のオーバードライブ付4速化なども行われています。
そんな初代レパードは、販売終了までに累計で7万887台が新車登録され、初代モデルとしては大きな成功を収めました。
1-2 新高級スペシャリティカーと位置付けられたレパードTR-X
初代レパードには日産チェリー店向けの姉妹車、レパードTR-X(トライエックス)も設定されました。
キャッチコピーは前期が「TR-X アメリカ」後期が「頂点は感動」と、レパード本体とは異なるポイントを訴求していたのが特徴です。
外観はレパードのフォグランプ内蔵異型ヘッドランプに対し、TR-Xでは規格型の角型4灯ヘッドランプを装着するなど、明確な差別化が図られています。
グレード構成も日産店向けレパードと比べて簡略化され、4ドアハードトップ200F/180Fと2ドアハードトップ180CFはMT仕様のみという構成でした。
また、標準グレードの280X-CFや2ドアハードトップ200X-SF標準車はTR-Xには設定されず、3ナンバーモデルは2ドア・4ドアともに280X-SF-Lの3速AT車のみという限定的な設定。
これは、日産店向けレパードの新世代ハイオーナーカーというキャラクターに対し、チェリー店向けTR-Xは新高級スペシャリティカーと位置付けられていたのが理由です。
2 先代より大きく方向性を変えた2代目 F31型

1986年2月に登場した2代目レパードF31型は、大きく方向性を変えたモデルです。
北米向けマキシマが「ブルーバードマキシマ」として国内市場にも投入され、競合のトヨタ・ソアラを強く意識した結果、姉妹車のTR-Xは廃止され、日産店とチェリー店ともにレパードの名称で統一。
さらにボディタイプも2ドアクーペのみとなり、4ドアの系譜は1988年9月発売のセフィーロへと引き継がれることになりました。
開発面では同時期のR31型スカイラインと基本設計を共有し、コスト抑制が図られています。
当初の開発主管はC32型ローレルやR31/R32型スカイラインの開発で知られる旧プリンス自動車出身の伊藤修令氏でしたが、組織変更により発表直前に山羽和夫氏へと交代しました。
広告展開では前期型に「private coupe(プライベート・クーペ)」「私は今、限りなく自由だ、限りなく豊かだ」後期型には「若いと言うだけでは、手に負えない、クルマがある」「美しいと云うだけでは、語り尽くせないクルマがある」「BIG 2DOOR」などのキャッチコピーを用い、高級感とスポーティさを強調。
CMでは映画「殺しのドレス」のテーマ曲を起用し、洗練されたイメージを演出しました。
2代目レパードは全車V型6気筒エンジンを搭載。前期型は185馬力のVG30DE型 3.0リッター DOHCエンジン、155馬力のVG20ET型 2リッター SOHCジェットターボエンジン、115馬力のVG20E型 2リッターエンジンの3種類をラインナップ。
後期型ではVG30DE型が最高出力が200馬力に向上したほか、VG20ET型に替わって210馬力VG20DET型 2リッター DOHCセラミックターボエンジンが採用されました。
さらに3リッターエンジン車にもターボモデルが追加され、255馬力を誇るVG30DET型 3リッター DOHCセラミックターボが搭載されました。
トランスミッションは、5速MTが前期型VG20E型を搭載するグレードのみに設定され、他はすべて4速ATとなっていました。
サスペンションはフロントがストラット式、リアがセミトレーリングアーム式で、上級グレードのアルティマには超音波センサーで路面状況を検知し、減衰力を自動調整する「スーパーソニックサスペンション」も装備されました。
エクステリアデザインは初代のイタリア的な近未来スタイルから一転。初代ソアラやBMWを思わせるクラシカルな方向性へと変化しました。
特にリアピラーからホイールハウスにかけて数字の6を描くような「エアフロー・フォルム」と呼ばれるバランスの良いデザインが特徴で、外板塗装の品質が向上したのも特徴です。
インテリアは航空機のコックピットをイメージした高級感あふれる設計で、エレクトロニクスメーターやオーディオなどを統合したデザインを採用。
助手席も運転席と同様に包み込むような構造で、収納スペースも充実しており、乗員への配慮が感じられる仕上がりでした。
そんな2代目レパードは発売当初、すでに確固たる地位を築いていたソアラの影に隠れて販売は苦戦していたものの、後に転機が訪れます。
ドラマ「あぶない刑事」シリーズの劇中車として起用され、主演の舘ひろし氏が演じる「タカ」の愛車として登場した黒のアルティマは強烈な印象を残し、今もなお中古車市場で高値で取引される人気モデルとしての地位を確立しました。
また、1989年には北米市場でインフィニティ・M30としてリリースされ、日本には存在しないコンバーチブルも設定されました。
このようにして1992年8月まで販売された2代目レパードの累計販売台数は3万8,543台でした。
3 日本車初の助手席エアバッグを全車標準装備した3代目 JY32型

1992年6月に登場した3代目レパードは、先代からさらに大きく方向転換。
ベースとなるはずだったスカイラインがR32型に世代交代するため、一度は開発中止となったものの、日産店のラインナップ欠落を懸念した要請により、インフィニティ・J30の日本国内向け導入という形で継続が決定。
これにより3代目レパードは、インフィニティブランドとしては初のEセグメントセダンとなり、日本国内向けにはV型8気筒エンジンも搭載されたことから、シーマの姉妹車のような位置づけとなりました。
結果としてボディタイプは4ドアセダンのみとなり、車名も「レパードJ.フェリー」へと変更。車のキャラクターが変わった点を明確にアピールしました。
キャッチコピーには「美しい妻と、一緒です」が採用されています。
このような経緯から3代目レパードは、トヨタ・クラウンにとどまらずセルシオまでも競合ターゲットとする本格的な高級車となり、ターゲット層も経済的余裕のある30代以上の子供を持たない層やカップル層へとシフトしました。
搭載エンジンは、200馬力のVG30DE型 3リッター V型6気筒 DOHCエンジンと、270馬力のVH41DE型 4リッター V型8気筒 DOHCエンジンの2種類が用意され、共に4速ATとの組み合わせを採用。特にV8エンジン搭載車は日産のV8搭載車種の中で最も軽量という特徴を持っていました。
装備面ではフェラーリやマセラティにも採用されていたイタリアのポルトローナ・フラウ製本革シートを約80万円でオプションに設定。通常の本革シートも約50万円と、セドリック/グロリアよりもさらにパーソナルな高級車としてのキャラクターを際立たせました。
ハンドリングに関しては、スポーツ性を抑えてラグジュアリー志向となった一方で、イギリス車ジャガーを意識した足回りとエンジン特性が特徴。セドリック/グロリアのグランツーリスモと同様の活発な走りを見せ、特にV8搭載車はそのパフォーマンスが高く評価されました。
技術面で注目すべきは、日本車として初めて助手席エアバッグを全車標準装備したほか、環境に配慮したR-134a冷媒を使用した「オゾンセーフエアコン」も全車採用するなど、先進性が追求されていた点です。
しかしながら、北米車に見られる発想の尻下がりのデザインは日本市場で受け入れられず、月平均販売台数は目標の3,000台に対して約100台前後と伸び悩み、総販売台数も約7,300台に留まりました。
一方、北米市場では月平均3,000台以上と好調な販売を記録しているなど、日本市場と国際市場での対比が興味深いモデルです。
4 シリーズ最後のモデル4代目 JY33型

出典元: Art Konovalov / Shutterstock.com
車名をレパードJ.フェリーから元の「レパード」に戻し、1996年3月にリリースされた4代目レパード。
バブル期の潤沢な開発費で生まれた先代から一転、バブル崩壊後の厳しい経営環境下で開発されたこのモデルは、Y33型セドリック/グロリアとの主要コンポーネントの共通化が大幅に進められ、事実上の姉妹車となりました。
そんな4代目レパードは、販売体制にも変化が見られます。
セドリックはローレル販売会社、グロリアはスカイライン販売会社が扱う中、レパードは先代からのブルーバード販売会社に加え、サニー販売会社でも販売されることになり、Y33型系は実質的に日産の全販売チャネルで取り扱われるという特異な展開となりました。
キャッチコピーには「新しい、高級のドアを開けませんか」「高級車の中で、一番自由でありたい」が用いられています。
エンジンラインナップも多彩になり、125馬力のVG20E型 2リッターV型6気筒 SOHCエンジンから270馬力を誇るVQ30DET型 3リッターV型6気筒 DOHCターボエンジンまで幅広く用意されました。
4代目からは先代のような輸出やインフィニティブランドでの展開はなく、日本国内専用モデルとして展開されたのもポイントです。
ボディタイプも4ドアピラードハードトップのみとなり、ドアパネルやインパネなどはY33型セドリック/グロリアと共通化されました。
エンジンは前期型が前出の270馬力のVQ30DET型、220馬力のVQ30DE型 3リッターV型6気筒 DOHC、160馬力のVG30E型 3リッターV型6気筒 SOHCの3種類。
後期型ではVQ30DE型とVG30E型に代わり、230馬力の日産初の直噴ガソリンエンジン、VQ30DD型 3リッターV型6気筒 DOHC(NEO-Di)エンジンのほか、190馬力のVQ25DE型 2.5リッターV型6気筒 DOHCエンジン、125馬力のVG20E型 2リッターV型6気筒 SOHCエンジンが加わりました。
さらに4WD車専用として235馬力のRB25DET型 2.5リッター直列6気筒 DOHCターボエンジンも設定されています。
グレード構成もセドリック/グロリアと似ており、トップグレードのXV-Gを筆頭に、XV、XR、XJという階層構成となってい他のが特徴です。
足回りはセドリック/グロリアのグランツーリスモと共通の仕様で、上級グレードにはコーナリング時の車両安定性を高める電動SUPER HICAシステムも採用されました。
実用性の高さが評価されたことから、個人タクシーとしても広く採用されるようになりました。特に後期型のXJをベースとしたタクシー仕様は多くの都市で見られるようになっています。
しかしながら、販売台数は前期型が約10,000台、後期型が約2,000台と振るわず、1999年6月のセドリック/グロリアのフルモデルチェンジおよびオーダーストップに伴い生産を終了。
2000年12月にはY34型セドリック/グロリアに統合される形で販売を終了し、レパードの20年にわたる歴史に幕を下ろすこととなりました。
日産レパードが高級車路線を模索した変遷
1980年から2000年までの20年間、時代とともに姿を変えてきたレパードは、日産の高級車開発において貴重な経験と知見をもたらしました。
初代の上級ハードトップから始まり、2代目のスポーティクーペ、3代目の高級セダン、そして4代目のセドリック/グロリアとの共通モデルへと、世代ごとに大きく方向性を変えながらも、常に時代の先端を行く高級車であり続けたのです。
モデルとしては4代を通して一貫したコンセプトを持ち続けることができず、確固たるブランド力を構築するには至りませんでしたが、そこで得られた経験は後のシーマやフーガ、スカイラインといった高級パーソナルカーの開発に大いに活かされています。
また、レパードの歴史は日本の自動車産業が成長し、バブル期を迎え、そして崩壊していく時代背景と重なり、当時の経済状況や消費者嗜好の変化を色濃く反映しているのも特徴と言えるでしょう。
初代から3代目までは比較的独自性の強いモデルとして展開されましたが、バブル崩壊後の4代目では経営効率化の波に飲まれ、セドリック/グロリアとの共通化が進み、最終的にはその系譜に吸収されるという結末を迎えました。
技術面でも、初代での世界初装備の採用、2代目のスーパーソニックサスペンション、3代目の助手席エアバッグ標準装備、4代目の直噴エンジン採用など、各世代で先進技術を積極導入する姿勢が印象的です。
日本の自動車史において、レパードのような変化を見せた高級車は珍しく、その独自の変遷は日本の自動車文化における貴重な一例と言えます。
特に2代目レパードは「あぶない刑事」劇中に登場したこともあり、30年以上経った今でもレストアやカスタマイズのベースとしてコアなファン層に支持され続けています。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。