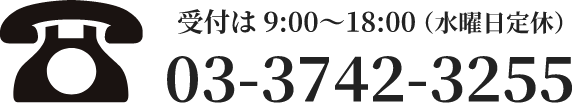2025年5月19日
車の安全装置「エアバッグ」正しく効果を発揮するために知っておきたいこと
ドライバーはもちろん、同乗者の身を守る安全装置として欠かせない「エアバッグ」。
事故の瞬間に瞬時に膨らみ、乗員を守るこの安全装置は、現在ではほとんどの車に標準装備され、現代の自動車には欠かせない存在となっています。
しかし、その仕組みや注意点、種類などについて理解している方は意外にも多くはありません。
そもそも、一般的にエアバッグと呼ばれている安全装置は、正式にはSRSはSupplemental Restraint System(補助拘束装置)を略した「SRSエアバッグ」と言います。
その名前が示す通り、エアバッグはあくまでシートベルトを「補助」する安全装置。
エアバッグは前面衝突時に瞬時に膨らみ、頭部や胸部への衝撃を大幅に軽減しますが、シートベルトと併用してはじめて、その効果が最大限に発揮されます。
交通事故総合分析センターが発表した2006年の調査によると、エアバッグが作動した事故でも、シートベルト非着用の場合は着用時と比較して死亡率がおよそ15倍も高くなるというデータがあります。
ところが、このような注意点について、実際にはあまり理解されていない部分が多いのも事実です。
今回は、エアバッグの歴史を踏まえて、基本的な仕組みから、おえておくべきポイントまでお伝えします。
目次
1 エアバッグのこれまでの歩みを振り返る

1-1 エアバッグの原型が誕生したのは1919年
現在では当たり前のように装備されているエアバッグですが、その歴史は意外と古く、最初の発明は100年以上前にまで遡ります。
1919年にイギリス人歯科医のハロルド・ラウンドとアーサー・パロットによって、エアバッグの原型となる特許がアメリカで申請され、1920年に承認されたのが最初です。
しかし、現代の自動車に広く採用されている火薬を用いたエアバッグシステム。この仕組みはもちろん、それ以降に登場したバネや空気圧縮技術を利用した仕組みは現代のエアバッグとは異なります。
現代の自動車に広く装備されるエアバッグシステムは、1963年に日本人の小堀保三郎氏によって発明されたものです。
小堀氏は航空機事故での生存率を高めるための装置として考案しましたが、当時の日本では奇抜すぎるアイデアとして相手にされず、さらには火薬の使用が消防法に抵触するという問題もあり、国内での開発は進みませんでした。
1-2 1970年代中頃から自動車への実用化を開始
一方、欧米では研究開発が進められ、1970年代中頃にアメリカで初めて実用化されます。
当時のアメリカではシートベルト着用の義務化に反発があり、シートベルトを締めなくても安全を確保できるシステムが求められていました。
1971年にフォード社が顧客車両にエアバッグを装着してモニター調査を行い、1973年にはゼネラルモーターズ(GM)が数車種でオプション装備として採用。
1980年にはダイムラー・ベンツ社が、Sクラスのオプションとしてエアバッグを装備しました。同社は開発時に取得した特許を「安全はすべてのメーカーが享受すべき」という理念の下、無償で公開。
これがエアバッグの普及が大きく進むきっかけとなります。
1-3 日本車初となる運転席へのエアバッグ搭載モデルはホンダ・レジェンド
そして1987年、日本車で初めてエアバッグを搭載したホンダ・レジェンドがリリース。
このモデルに装備されたエアバッグは、タカタとホンダの共同開発によるもので、装備されていたのは運転席のみでした。
日本車で最初に運転席エアバッグを全車標準装備としたのは1992年発売のホンダ・ドマーニとされています。
1990年代中頃からは日本でも急速に普及が進み、2009年には一部の安価な車種を除き、日米欧の大手自動車メーカーのほぼ全ての車種の運転席・助手席に標準装備されるようになりました。
エアバッグの歴史で特筆すべきは、発明者である小堀保三郎氏の悲劇的な最期です。
同氏は、現代では広く普及したエアバッグの仕組みを生み出したものの、特許を有していた期間に実用化・普及されなかったため、それによる収入を得ることができませんでした。
研究費などが原因で借金を抱えた小堀氏は、エアバッグの世界的な普及を知ることなく、1975年8月30日に夫婦でガス心中してしまいます。
皮肉にも命を守る装置を発明した方が、その恩恵を受けることなく生涯を終えたのです。
その後の2006年、小堀氏は現代の車において欠かすことのできないエアバッグを発明したその功績が讃えられ、日本自動車殿堂に殿堂入りしました。
2 エアバッグの仕組み

本項では、エアバックの仕組みと注意点についてお伝えします。
2-1 エアバッグが動作する仕組み
エアバッグシステムは主に以下のパーツで構成されています。
- 加速度センサー
- エアバッグ本体
- ECU(電子制御装置)
- インフレーター(ガス発生装置)
事故時のエアバッグ作動の流れは次のようになります。
- 車両が衝突すると加速度センサーが反応し、エアバッグECUに情報が送られる
- エアバッグECUが加速度センサーの情報を加味し、エアバッグの展開を判断
- 展開が決定した場合、エアバッグECUがエアバッグモジュールに展開の指示を出す
- インフレーター内の火薬が爆発し、発生したガスによって0.01秒単位という瞬時のスピードでエアバッグを膨らませる
- 収納部を押し破り、エアバッグが展開する
- 完全に膨張した後、エアバッグ背面に設けられた排出口からガスが抜け、速やかに収縮する
エアバッグがこの動作によって衝撃を吸収するメカニズムは、運動エネルギーの変換です。
車のブレーキが運動エネルギーを熱エネルギーに変換することで制動力を生み出すのに対し、エアバッグは人体の運動エネルギーを、バッグ内のガスの運動エネルギーに変換することで衝撃を吸収します。
エアバッグの展開速度はおよそ100~300km/hにも達し、衝突からわずか0.03~0.05秒程度という驚異的なスピードで膨張。人体がエアバッグに衝突するとエアバッグの容積が減少し、内部の圧力が高まると同時に排出口からガスを勢いよく噴出することで、衝突のエネルギーを吸収する仕組みです。
この展開速度により、乗員がハンドルやダッシュボードに衝突する前に間に入り、致命的な怪我を防ぐことができます。
なお、エアバッグが作動するのは一定以上の衝撃を受けた場合のみです。
フロントエアバッグの場合、コンクリートの壁など強固な構造物に約20~30km/h以上の速度で正面衝突したときなどに作動します。
ただし、衝突角度や衝突の仕方によっては、大きな衝撃でも作動しないことがあります。
2-2 理解すべきエアバッグの注意点
エアバッグは、命を守るという点において非常に有効な安全装置ですが、正しく使わないとその効果を十分に発揮できないどころか、さらに危険な場合もあります。
そのため、以下の注意点を守ることが大切です。
- シートベルトを必ず着用する
繰り返しになりますが、エアバッグはあくまでもシートベルトの補助装置です。エアバッグが装備されていても、シートベルトの着用は絶対に欠かせません。 - エアバッグ周辺に物を置かない
インパネやダッシュボードなど、エアバッグが格納されている場所に物を置いたり、飾りをつけたりするのは危険です。エアバッグが作動したときに物が吹き飛ばされて乗員にぶつかり、重大なケガを負う可能性があります。展開の妨げとなる恐れのあるステッカーなどを貼り付けるのもやめましょう。 - 正しい姿勢で座席に座る
エアバッグは正しい姿勢で座っていることを前提として設計されています。そのため、体型に合わせずに座席を大きくリクライニングさせている場合などは、エアバッグの性能が発揮されません。また、エアバッグは非常に早いスピードで膨らむため、ハンドルに近づきすぎる、格納されている場所に足を乗せる、手や足を近づける、もたれかかるといった姿勢にも危険が伴います。 - 助手席にチャイルドシートを乗せるのは危険
エアバッグは大人が座ることを前提とした設計のため、助手席にチャイルドシートを取り付けた場合には効果が発揮されないことや、被害を拡大させてしまうことがあります。特に助手席に後ろ向きのチャイルドシートを設置することは絶対にやめましょう。エアバッグが膨らんだときの衝撃がチャイルドシートの上部にかかり、子どもが助手席に押し付けられたり、チャイルドシートが弾き飛ばされたりするなど、命に関わる危険があります。 - エアバッグが原因で怪我をする場合もある
エアバッグが膨らむ際に発生するガスそのものは特に有害なものではありません。ただし、膨張時にかすり傷や、打撲、骨折、火傷などの軽微な怪我をする可能性があります。これらの傷害はエアバッグがなかった場合と比較するとはるかに軽微なものです。 - エアバッグの特性を理解する
エアバッグには以下のような特性があることを理解しておきましょう。- フロントエアバッグやサイドエアバッグは膨らんだ後すぐにしぼむため、多重衝突事故のように衝突後さらに衝撃を受けた場合には防ぐことができない。
- 縁石や路肩、車止めに乗り上げた、溝や穴に落ちた、地面に強くぶつかったなどの場合、事故でなくてもエアバッグが開く可能性がある。
- 電柱などに衝突し車の前面の一部が極端に変形するような事故や、車高の高いトラックの荷台の下に潜り込むなど、衝撃が徐々に伝わるような場合、車が側斜めに衝突した場合、衝突しながら大きく移動した場合など、衝突事故が起きてもエアバッグが開かないことがある。
3 基本的なエアバッグの種類と役割

現代の自動車には様々な種類のエアバッグが搭載されています。それぞれの特徴と役割について詳しく見ていきましょう。
- フロントエアバッグ(運転席/助手席)
最も一般的に知られるエアバッグで、前面衝突時に瞬時に膨らみ、ドライバーや助手席の乗員の頭部や胸部がダッシュボードやハンドルに打ちつけられるのを防ぐ仕組みです。現行車にはほとんど全てのモデルで標準装備されています。
運転席エアバッグはステアリングホイール内部から膨らみ、ハンドルの向きに関係なく常に同じ性能を発揮できるよう設計されているのがポイント。カバーは円周方向に開き、エアバッグは乗員へのダメージを抑えつつ放射状に展開するよう、折り畳み方が工夫されています。
一方、助手席エアバッグはダッシュボードの中に格納されており、展開時の衝撃による加害を避けるため、直接乗員に向かうのではなく、フロントウインドウや天井に沿って上から下へ広がるよう設計されています。 - サイドエアバッグ
通常はシートの背もたれに格納されており、車の側面から衝撃を受けたときに、ドアと乗員の隙間を埋めるように膨らみ、胸部や腹部などへの衝撃を軽減するエアバッグ。側面衝突では車体のノーズのような衝撃吸収スペースがないため、非常に短い時間で展開する必要があります。運転席と助手席、近年では後部座席用もあり、オプションでの搭載となる車種が多いものの、標準装備している車も増えつつあ流状況です。 - サイドカーテンエアバッグ(カーテンシールドエアバッグ)
ドア上部の車体の屋根に沿った部分(ルーフライン)に設置され、側面から衝撃を受けたときにカーテンのように窓全体を覆うように広がるエアバッグ。運転席から後部座席まで広い範囲をカバーする最も大きなサイズのエアバッグです。主に乗員の頭部保護を目的とし、作動後もしばらく膨らんだ状態を維持することから、横転した際に乗員が車外に投げ出されるのを防ぐ役割も持ちます。大容量のインフレータ(ガス発生器)が使われ、必要に応じて2本搭載されることもあります。 - 後席センターエアバッグ
後部座席の中央に設置されており、側面衝突時に後部座席の左右の乗員同士がぶつからないようにする役割があります。 - ニーエアバッグ
ステアリングコラムまたはインパネの下部から膨らみ、衝突時に乗員の下肢を保護するとともに、体が前方に滑り出すのを防ぐ役割があります。 - シートクッションエアバッグ
シート座面下に装備されており、衝突時に座面前部が押し上がることで腰部の前方移動を抑止し、下腹部への衝撃を緩和します。 - その他の特殊なエアバッグ
- リアウインドウカーテンシールドエアバッグ
追突時に後席頭上に展開し、後席乗員の頭部・頸部を保護します。 - シートベルトエアバッグ
シートベルト本体にエアバッグが内蔵されており、衝突時に肩ベルトの一部が膨らんで頸部と胸部を保護します。 - ドアマウントカーテンエアバッグ
オープンカーなど、通常のカーテンエアバッグが搭載できない車両に採用されます。 - 歩行者保護エアバッグ
歩行者との衝突に備えて、ボンネットやフロントガラスの外側に沿って膨らむエアバッグです。
- リアウインドウカーテンシールドエアバッグ
エアバッグ技術は年々進化しており、より効果的に乗員を保護するための新しいタイプのエアバッグが開発されています。
現在の高級車ではこれらの多様なエアバッグを組み合わせて搭載することで、あらゆる方向からの衝突に対応できる全方位的な保護システムを構築しています。
大切な命を守るために知っておきたいエアバッグのこと
エアバッグは、シートベルトと併用することで事故時の致命的な傷害を大幅に軽減できる重要な安全装置です。
ただし、正しく効果を発揮するためには、以下の4つのポイントを踏まえ、エアバッグの特性を正しく理解しましょう。
- 必ずシートベルトを着用する
- シートを適切な位置に調整し、ハンドルや助手席のダッシュボードから適度な距離を保つ
- エアバッグ付近に物を置かない
- チャイルドシートは後部座席に設置する
エアバッグ技術は日々進化しており、より効果的で多様な保護機能を持つエアバッグが開発されています。
しかし、どんなに優れた安全装置も、それを正しく使わなければ意味がありません。
また、エアバッグには点検や交換の必要性も忘れてはいけません。一度作動したエアバッグは再利用できず、経年劣化によって性能が低下する可能性もあります。
車検時にはエアバッグ警告灯が正常に点灯・消灯するかの確認も行われます。
私たちの命を守ってくれるエアバッグの仕組みと正しい使い方を理解し、万が一の事故に備えましょう。そして何より、事故に遭わないよう、安全運転を心がけることが最も大切です。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。