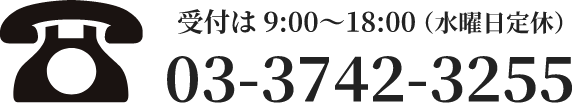2025年5月5日
意外な渋滞の原因について|約12兆円の経済損失を生む社会問題の仕組みを知る
日頃から車を利用する方にとって、渋滞は避けられない問題です。
特に悩ましいのは、渋滞の先頭まで辿り着いてみると、そこには事故や工事などの明確な原因が見当たらず、いつの間にか交通がスムーズに流れ始めるという現象です。
「何もないのになぜ渋滞していたのだろう?」と不思議に思った経験があるドライバーも少なくないはず。
そもそも渋滞の定義は、高速道路を管理するNEXCOによると「時速40km以下で低速走行あるいは停止発進を繰り返す車列が、1km以上かつ15分以上継続」した状態を指します。
このような渋滞には、実はさまざまな原因と複雑なメカニズムが存在し、単純に車が多いというだけが原因ではありません。
渋滞は大きく分けて交通集中渋滞、工事渋滞、事故渋滞の3種類とされ、道路構造やドライバーの運転パターン、さらには心理的要因などが絡み合って発生します。
そして、現代社会においては、渋滞における経済損失も問題視されています。
日本国内における渋滞による経済損失は年間でおよそ12兆円とも言われており、これは社会全体にとっても大きな課題です。
今回は渋滞の原因やメカニズムを見ていきます。
目次
1 事故や工事がなくても渋滞が起きる様々な原因

渋滞といえば事故や工事を思い浮かべる方も多いでしょうが、実は特別何もない状況でも発生します。
前述の通り、渋滞が起きる原因は大きく分けて3つあります。
1つ目の交通集中渋滞は、道路の交通容量を超える車が集中することで発生する渋滞です。
2つ目の工事渋滞は、文字通り道路工事によって車線規制が行われることで発生する渋滞を指します。
3つ目の事故渋滞は、交通事故によって道路が封鎖されるなど、交通状況に支障が出ることで起こる渋滞です。
これらの中で最も頻度が高いとされているのは交通集中渋滞。特に連休中の高速道路や朝夕のラッシュ時における一般道では、道路の処理能力を超える車両が集中することが原因で渋滞が起きます。
交通集中渋滞が発生する根本的な原因は、主に車両密度の増加と走行速度のばらつきの2つ。
道路には一定の交通容量があり、それを超える車両が流入すると車間距離が縮まり、スピードのわずかな変化が後続車に増幅して伝わることで渋滞が発生します。これは「サグ部」と呼ばれる緩やかな上り勾配や、車線減少区間、合流部などで特に起こりやすい現象です。
また、心理的要因も大きく影響します。近年問題となっている「あおり運転」などの攻撃的な運転行動はもちろんのこと、必要以上に慎重な運転も全体の交通流を乱す原因となります。
特に渋滞時にはドライバーがイライラし、無意識のうちに車間距離を詰めたり急ブレーキを踏んだりする行動が増え、さらに渋滞を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
そして、特筆すべきは「自然渋滞」と呼ばれる現象です。これは事故や工事などの物理的な障害物がなくても発生する渋滞のことを指します。
交通工学の研究によると、道路の交通量がその処理能力の約8割を超えると、わずかな速度変化が増幅されることによって渋滞が発生することが明らかになっています。
日本の首都高速道路や東名高速道路などでは、この自然渋滞が日常的に発生しており、特に休日や連休には顕著です。
自然渋滞の実験では、円形のコースを複数の車が走行するだけでも、車両密度が一定を超えると必ず渋滞が発生するという興味深い結果が証明されています。
この現象は「交通流の不安定化」と呼ばれ、一度渋滞が発生すると、その原因となった車両がすでにその場所を通過した後も渋滞が持続するという特性があります。
つまり、ドライバーの運転行動、特にブレーキの踏み方や車間距離の取り方などによって交通流が不安定になってしまうと、それが渋滞の大きな原因となってしまうのです。
2 渋滞が生まれるメカニズム

渋滞がどのようにして発生し、拡大していくのか、そのメカニズムを理解することは渋滞対策の第一歩だと言えます。
まずは渋滞発生の基本的なプロセスを見ていきましょう。
渋滞の原因を理解するうえで、最も重要とされている概念は「減速波」です。
例えば前方の車がブレーキを踏んだ場合には、当然ながら後続車もブレーキを踏みます。
その際、必ず生じるのが反応の遅れです。一般的な反応時間は0.5〜1秒程度と言われていますが、この遅れにより後続車は前方車両よりも強くブレーキを踏む傾向があります。
これが連鎖的に起こると、後方に行くほど車の減速度が大きくなり、最終的には完全に停止する減速波が発生します。
この減速波が後方に伝わる速度は、交通量の多さに比例して速くなるのがポイントです。そして、高速道路における渋滞では、この波が時速15〜20kmほどの速さで後方に伝わっていくことが観測されています。
次に押さえておきたいのが「ボトルネック効果」と呼ばれる概念。
道路の一部区間で交通容量が低下すると、そこを境に渋滞が発生します。例えば3車線から2車線に減少する箇所では、理論上は交通容量が3分の2に減少するはずですが、実際には車線変更による混乱や心理的要因から、それ以上に大きく容量が低下するのが特徴です。
このような複雑なメカニズムが絡み合い、一度渋滞が発生すると容易には解消されません。
特に交通量が多い状況では、渋滞の原因が解消された後も長時間渋滞が継続することがあります。
このメカニズムを知ると、急ブレーキを避ける、一定の速度を保つなどの行動が、全体の交通流改善に貢献していることが理解できます。
制限速度を上げ、車のスピードを出すことよりも、全体として渋滞を発生させない運転を心がけることこそが、スムーズなドライブにつながると言えるでしょう。
3 気になる渋滞の先頭の真実、道路構造が引き起こす渋滞の意外なワケ

高速道路や一般道で長い渋滞に巻き込まれた際、誰しもが一度は持つであろう「渋滞の先頭には何があるのだろう?」という疑問。
実は、渋滞の先頭には前項の自然渋滞の原因はもちろん、必ずしも事故や工事があるわけではなく、道路構造そのものが原因となっているケースも多くあります。
渋滞が発生しやすい代表的な例を見てみまましょう。
- サグ部
サグ部とは緩やかな上り坂のことで、ドライバーが意識しないうちに速度が低下しやすい場所です。特に大型車は登坂能力が弱いため、速度低下が顕著になります。 - 車線減少区間
3車線から2車線、あるいは2車線から1車線に減少する箇所では、車線変更のための減速や車線をなかなか譲らない車の存在によって交通流が乱れ、渋滞が発生します。合流が円滑でない場合には、車線が減少する手前から渋滞が発生することもあります。 - 合流部
本線と合流車線からの車両が交錯する場所では、お互いの車間距離を確保するために減速が生じ、それが渋滞の引き金となります。特にICやJCT付近では、合流のための減速と本線の交通量増加が重なり、渋滞が発生しやすい環境です。 - トンネルの入口
トンネル内では、閉鎖感や照明条件の急変によって速度を落とすドライバーが多く、これが集団で起きると渋滞につながります。 - カーブ区間
見通しの悪いカーブでは前方の状況が把握しづらいため、ドライバーは本能的に速度を落とします。それが減速波となり、渋滞の原因となります。 - インターチェンジ周辺
車線変更や速度調整が頻繁に行われる高速道路の出入り口付近は、交通流が乱れやすい状態です。特に休日や連休には、観光地へ向かう車が集中するインターチェンジで渋滞が発生しやすいです。 - 料金所付近
ETC普及により現象したものの、現在でも料金所手前では減速する車両が多く、渋滞の原因となっています。ETCレーンとー般レーンの混在も交通流を複雑にしている原因です。
これらの要因が複合的に作用することで、一見何もないように見える場所でも渋滞が発生・拡大して行きます。
道路設計時にはこれらの要素を考慮した対策が取られているものの、交通量が想定を超えた場合、渋滞は避けられません。
4 渋滞を回避するために意識すべきポイント

渋滞はドライバーひとりひとりが気をつけることで軽減することができます。
最も重要なのは「適切な車間距離の確保」です。
車間距離が短いと、前方車両のわずかな速度変化にも反応せざるを得なくなり、ブレーキの連鎖反応を引き起こします。高速道路では、前方車両が通過した地点を通過するまでの時間つまり、車間時間を少なくとも2秒以上確保することが推奨されています。
次に心がけるべきは「速度の平準化」です。
急加速・急減速を避け、できるだけ一定の速度で走行することで、後続車への影響を最小限に抑えられます。特に渋滞中やその最後尾に接近する際は、急ブレーキを避け、エンジンブレーキを活用した緩やかな減速を心がけることが大切です。
車線合流時の「ジッパー合流」も効果的です。
車線減少部や合流部では、最後まで両方の車線を使い切り、合流ポイントで1台ずつ交互に合流するジッパー合流が理想的とされています。早めに車線変更すると有効な車線が減ってしまい、かえって渋滞を悪化させることになります。
カーナビを活用した「情報の活用」も欠かせません。
近年のカーナビやスマートフォンのアプリでで、渋滞情報をリアルタイムに入手できます。事前に渋滞箇所を把握し、可能であれば迂回ルートを検討することも有効です。ただし、大勢が同じ迂回路を選択してしまうと、今度はそちらが渋滞する二次渋滞が発生することもあるため注意が必要です。
「時間帯の選択」も重要なポイントです。
朝夕のラッシュ時や連休の初日・最終日は渋滞が予測されるため、可能であれば出発時間をずらすことも検討しましょう。特に高速道路では、深夜から早朝にかけての時間帯は比較的空いていることが多いです。
最後に「自動運転・運転支援技術の活用」も効果的です。
「ACC(アダプティブクルーズコントロール)」や「LKA(レーンキーピングアシスト)」などの運転支援技術は、人間よりも精密に車間距離や速度を制御できるため、渋滞の軽減に大きく貢献します。これらの技術が広く普及すれば、将来的には渋滞が大幅に軽減される可能性もあります。
運転時にはこれらのポイントを意識することで、ドライバーひとりひとりが渋滞軽減に貢献できることを心に留めておきましょう。
社会全体で取り組むべき課題「渋滞」を考える
渋滞は単なる不便さや時間のみの問題ではなく、経済的損失に加え、環境負荷の増大や事故リスクの上昇など、社会全体に大きな影響を与える問題です。
日本の渋滞による経済損失は年間約12兆円とも言われています。この問題の解決には個人レベルの取り組みだけでなく、社会インフラの整備や交通システムの改善など、多角的なアプローチが必要とされるでしょう。
しかし、ドライバーが渋滞の発生メカニズムを理解することも重要です。
適切な車間距離の確保、速度の平準化、ジッパー合流の実践など、一見すると些細な心がけがに見えますが、私たちひとりひとりが心がけることで大きな効果を生み出す可能性があります。
加えて、移動時間の分散やテレワークの推進など、社会全体を通した取り組みも重要です。
将来的には自動運転技術の発展やAIを活用した交通管制システムの導入により、渋滞問題は大きく改善される可能性はあるものの、私たちドライバーが渋滞について理解し、思いやりを持って道路を共有することが、この問題に対する最も身近な解決策と言えるでしょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。