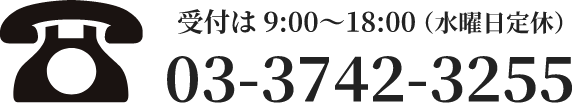2025年4月16日
歴代シーマ、頂点を目指した日産の名車の軌跡
1988年、日産「シーマ」は、高級セダン「セドリック」「グロリア」の上級仕様として、初代がリリースされました。
スペイン語で「頂上」「高み」を意味する「cima」に由来したこの車名には、初代開発責任者の三坂泰彦氏が子供の頃に父から買ってもらった腕時計「シーマ(Cyma)」への思い入れが込められているといいます。
そんな初代シーマはバブル景気の只中、全車3ナンバーの全長4,890mm、全幅1,770mmの大型ボディに3.0リッターの大排気量V6エンジンを搭載した大型高級セダンです。
発売当時は、車両価格が400万円を超えていたにも関わらず、初めの1年間だけで3万6,400台が販売され、初代の4年間の販売台数は12万9,000台にも及びました。
当時の高級品需要を象徴するこの出来事は「シーマ現象」と呼ばれています。
堂々たる佇まいでハイソカーの頂点に立つモデルとして登場したシーマは、まさに日産が目指した最高峰・頂点を体現したモデルと言えるでしょう。
今回はバブル期に登場し、当時の高級車の頂点に位置付けられた日産「シーマ」の5代にわたる歴史を振り返ります。
目次
1 初代 FPY31型

1988年1月、バブル景気の絶頂期に登場した初代シーマは、Y31型セドリック/グロリアと共通のプラットフォームを採用しながらも、高級車としてのキャラクターをさらに強く打ち出したモデルです。
初代シーマは、モーター店系列向けの「セドリックシーマ」と、プリンス店系列向けの「グロリアシーマ」の2つの名前でラインナップされていたのがポイント。
京都・三千院の勢至菩薩坐像をモチーフにデザインされ、薄型フロントと丸みを帯びた滑らかなボディラインが特徴的な、全車3ナンバーサイズのみの上級車として誕生しました。
実は初代シーマは、ハイソカーブームにより当時の日本で高まっていた高級志向を背景に急遽開発が進められたモデルでした。
本格的な3ナンバー車への需要の高まりや、ライバル車トヨタ・クラウンの3ナンバー化の動き、さらには税制改革の気運もあり、日産は迅速に対応する必要がありました。
セドリック/グロリアとの開発スケジュールの兼ね合いもあり、半年遅れでのリリースとなりました。ところが、結果としてこの時間差が功を奏し、ベースとなったセドリック/グロリアとは一線を画した存在として別格のイメージを獲得することに成功したのです。
エンジンラインナップは、200馬力のVG30DE型 V型6気筒DOHC NAと、255馬力のVG30DET型 V型6気筒DOHCターボの2種類を設定。
特にこのターボエンジンには興味深いエピソードがあります。
開発当初は自然吸気エンジンのみが検討されていましたが、ライバル車をクラウンではなくソアラに定めた開発チームは、走りで負けるわけにはいかないと判断。白羽の矢が立ったのが、当時F31型レパード用に開発中だったVG30DETエンジンでした。
本来ならばレパードに初搭載される予定だったこのエンジンですが、シーマ開発担当者の熱意に押される形で、初採用の座をシーマに譲ることになりました。
デザイン面ではセドリック/グロリアと同じく、開放的なピラーレスドアを採用。さらに、フード中央にはアカンサスの葉を模したエンブレムを配置するなど、随所に高級感を演出する要素が盛り込まれました。
このようなラグジュアリーな佇まいと強力なパワーユニットを併せ持った初代シーマは、発売とともに大きな反響を呼び、発売から初年度で3万6,400台販売という、高級車としては異例のセールスを記録。
販売が終了した1991年までの約4年間で累計販売台数は12万9,000台にも及びました。
2 2代目 FY32型

1991年に登場した2代目シーマは、より洗練された高級セダンへと進化を遂げたモデルです。
1997年までの約7年間販売され、この代からは「セドリック・シーマ」「グロリア・シーマ」の名称が廃止され、シーマとして統一されました。
デザインは、初代のピラーレスドアからセンターピラーを備えた形状へと変更されたのが特徴的。これは後席の居住性向上とボディ剛性の強化を目的としたものとされ、先代よりもさらにフォーマルかつ重厚なデザインへと進化しました。
パワーユニットには、トヨタのセルシオやクラウンに対抗すべく、VH41DE型 4.1リッター V型8気筒DOHCエンジンを新たに搭載。
この排気量4.1リッターという税制上不利なエンジンが採用された背景には、初代ターボモデルで高評価を得ていた「力強い加速感」を自然吸気で実現するためにこの排気量が必要だったことや、北米市場向けの日産インフィニティQ45との販売戦略上の兼ね合いがあったとされています。
インテリアも大幅に刷新され、バブル景気を象徴するような豪華さが随所に見られる仕様になりました。
タン色の本革シート、デザイン重視のアナログ時計、楡・玉杢模様の本木目パネル、リヤデュアルパワーシートなど、上質な素材と装備が惜しみなく採用されています。特に車内20ヶ所に設置されたライトが状況に応じて点灯する「トータルコーディネート照明」は印象深い装備です。
1992年には、前後のトルク配分を高度に制御するフルタイム4WD機構「アテーサE-TS」を搭載した「S-four」がラインナップに加わりました。
さらに1993年には、初代と同じVG30DET型 V型6気筒DOHCターボエンジンを搭載した「ツーリング」グレードも追加され、ラインナップがさらに充実します。
1996年、2代目シーマはFR車が3代目へとモデルチェンジしましたが、4WD車は1997年まで販売が継続されました。
3 3代目 FY33型

1996年に登場し、2001年まで販売された3代目シーマは、バブル崩壊後の日本市場において、より成熟した高級セダンとしての新たな道を歩み始めたモデルです。
この代は、初代インフィニティQ45が1997年に国内販売を終了したことから、その後継車種としての役割も担うことになりました。
デザイン面では、初代や2代目の流れを汲むクラシカルな印象から一転し、ドイツの高級車を思わせる端正で引き締まったスタイリングへと変貌を遂げています。
パワーユニットは、先代から引き続きVH41DE型 4.1リッター V型8気筒DOHCエンジンに加え、VQ30DET型 3.0リッター V型6気筒DOHCターボエンジンの2種類がラインナップされました。
3代目シーマの最大の特徴は、安全装備の充実にあります。日本車初となるSRSサイドエアバッグを全車に標準装備したほか、1997年のマイナーチェンジでは後席サイドエアバッグを追加。1998年のマイナーチェンジでは、やはり日本車初となる前席アクティブヘッドレストや後部中央席の3点式シートベルトを装備するなど、安全性向上に積極的に取り組んだモデルでした。
さらに1999年には、国産車としては初めての自動ブレーキング機能を持つ車間自動制御システムを搭載したグレード41LV-Zをラインナップに追加。これは現在の自動運転技術の先駆けとなる画期的なシステムでした。
3代目シーマは、バブル期の華やかさから一転し、本質的な価値を追求した高級車へと進化。技術的先進性と安全性を両立させることで、新たな時代のフラッグシップセダンとしての地位を確立しました。
4 4代目 F50型

2001年1月に登場した4代目シーマは「Dynamic&Modern 時代を切り拓く新しいカタチ」をコンセプトに開発され、グローバルに通用する高級車を目指した意欲的なモデルです。
プラットフォームには3代目インフィニティQ45や4代目プレジデントと共通の「新世代LLクラスプラットフォーム」を採用。歴代から継承してきた圧倒的な性能はそのままに、日産のフラッグシップに相応しい最先端技術を惜しげもなく投入しています。
パワーユニットは、VQ30DET型 3.0リッターV型6気筒DOHCターボと、ガソリン筒内直接噴射システム「NEO Di」を採用したVK45DD型 4.5リッターV型8気筒DOHC直噴の2をラインナップ。
特にV8エンジン搭載モデルには、小型プロジェクターランプを中央に1つ配置し、それを取り囲むように6つのランプを配置した「バルカンヘッドライト」と呼ばれる特徴的なデザインが採用されています。
先代と同じく、4代目シーマの最大の特徴は先進安全装備の充実にあります。
現在では多くの車種で見られるドアミラーウインカーを国産車で初めて採用したことに加え、CCDカメラで白線を認識し車線からの逸脱を防止する「レーンキープサポートシステム」を世界初装備。
このシステムとレーダークルーズコントロールの組み合わせにより、約100km/h以下の走行時に先行車を自動追尾する機能を実現しました。これは今の自動運転技術の先駆けとなる画期的なシステムだったと言えるでしょう。
2001年12月の一部改良では、助手席パワーオットマンの採用や本木目・本革巻コンビステアリング、電子キーの全車標準装備化など、さらなる装備の充実が図られました。
2003年のマイナーチェンジではV8エンジンがVK45DE型へと変更され、インテリジェントブレーキアシストや前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト、アクティブAFSなど、安全装備がさらに強化されています。
2008年のマイナーチェンジでは外観が変更され、フェンダーミラーの廃止やフロントマスク・テールランプのデザイン変更などが実施されました。また、フロント・リアバンパーの拡大により全長は5,120mmとなり、さらに大型化しています。
長きにわたり日産の技術と美学を体現してきた4代目シーマですが、2010年8月には同じ新世代LLクラスプラットフォームを採用したプレジデントとともに生産が終了。
初代から続く22年の歴史に幕を下ろすこととなりました。しかしながら後の2012年、5代目として復活を遂げることになります。
5 5代目 HGY51型

出典元: Yosuke Saito / Shutterstock.com
2012年5月、4代目から約1年9ヶ月の時を経て、シーマは5代目として復活を遂げました。
5代目は、シーマ史上初となるハイブリッド専用モデルへと進化したのが最大の特徴です。環境性能と走行性能の両立を目指し、歴代から継承してきた圧倒的な走りと、フラッグシップにふさわしい居住性・快適性を兼ね備えています。
そんな5代目シーマに採用されているのは、ベース車種となる2代目フーガハイブリッドと同様のVQ35HRエンジンに、1モーター2クラッチのパラレル方式を組み合わせた「インテリジェント・デュアルクラッチ・コントロール」。変速機にはジヤトコ製マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッションが採用されています。
このハイブリッドシステムは比較的シンプルな機構でありながら、疑似クリープ走行、モーター単独走行、エンジン+モーターによる全開加速、エンジン走行+充電、回生ブレーキなどの切り替えをスムーズに行うことが可能でした。また、トルクコンバーターを介さない直結式を採用することで、従来のハイブリッドシステムよりも高い伝達効率を実現しています。
ハイブリッドシステム搭載により車両重量は増加したものの、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング機構、電動油圧式電子制御パワーステアリングなどの採用により、燃費性能は大幅に向上。平成27年度燃費基準+20%および、2015年4月に設けられた平成32年度燃費基準+10%を達成しました。
高級車としての魅力を損なうことなく、環境性能も高めるという難しい課題をクリアしたのです。
2017年には安全装備を中心としたマイナーチェンジが実施されました。FCW(前方車両接近警報)は自車から2台先の車両にも対応したインテリジェントFCW(前方衝突予測警報)に進化。また、バックビューモニターとサイドブラインドモニターを一体化し、移動物検知機能を備えたインテリジェント アラウンドビューモニターへと性能が向上しました。
さらに、インテリジェント エマージェンシーブレーキ、インテリジェントBSI(後側方衝突防止支援システム)およびBSW(後側方車両検知警報)、インテリジェントBUI(後退時衝突防止支援システム)が標準装備されるなど、先進安全装備が一層充実。
ハイブリッド技術と最先端安全技術の融合により、新時代の高級車としての地位を確立しました。
しかしながら、セダンの人気低迷や、2022年9月1日から適用される騒音規制をクリアできないことなどが原因となり、5代目シーマは2022年にベースモデルのフーガとともに販売を終了。
輝かしい34年の歴史に終止符を打ちました。
バブル経済を象徴する日産の名車「シーマ」の34年の栄光
1988年、バブル景気絶頂期に登場した日産シーマは、セドリック/グロリアをベースに開発された高級車として、日本の自動車史に大きな足跡を残しました。
頂点を意味する名を冠したこのモデルは、まさに日産の技術の粋を集めたフラッグシップモデルと言えるでしょう。
初代は発売と同時に予約が殺到し、販売台数が供給を上回る「シーマ現象」を引き起こし、バブル期の高級車ブームを象徴する存在となりました。
2代目は4.1リッターV8エンジンを搭載し、より豪華で重厚な高級車へと進化。3代目では日本車初のサイドエアバッグや自動ブレーキング機能など、安全技術でも先駆的な役割を果たしました。
4代目はさらなる先進技術を導入し、世界初の「レーンキープサポートシステム」を搭載。一度は2010年に生産が終了しましたが、2012年に5代目として復活を遂げます。
最後の5代目はハイブリッド専用モデルとなつつも、先代までの性能を受け継ぎ、時代の変化に対応しながらも高級車としての威厳を保ち続けました。
しかしながら、セダン市場の縮小や騒音規制など、移り変わる時代には抗えず、2022年に34年の歴史に幕を下ろすこととなりました。
その栄光の歴史はバブル期の象徴から先進安全技術の結晶、ハイブリッド高級車へと変遷し、国内の自動車を牽引したモデルとして、今もなお多くの自動車ファンの記憶に刻まれています。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。