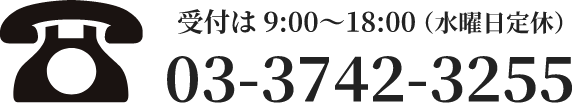2020年1月27日
鉄仮面の愛称で人気の6代目スカイラインとは?愛称の由来や特徴に迫る!
1957年の初代登場から2013年の13代目まで、約60年もの長期間にわたってバージョンアップやモデルチェンジを繰り返してきた日産・スカイライン。
今回は、鉄仮面の愛称で親しまれた6代目R30型スカイラインについて解説します。
なぜ6代目スカイラインは鉄仮面と呼ばれるようになったのか、その由来について、6代目スカイラインの誕生や進化の歴史とともに振り返りましょう。
目次
1 6代目スカイラインは「ニューマン・スカイライン」の愛称で親しまれた

ケンメリの大ヒット、続くジャパンでも広告宣伝が大流行した歴代スカイライン。続く6代目のR30型では、ついにアメリカ人俳優であるポール・ニューマンを広告キャラクターに抜擢されます。
時代は1981年であり、景気は右肩上がり。明日はきっと今日より豊かになると信じられてきた世相を反映した結果といえるでしょう。
このことから、当初は「ニューマン・スカイライン」の愛称で親しまれました。
2 DOHCの復活

1981年8月に発売された6代目ニューマン・スカイラインは、基本的にジャパンから大きな変更はありませんでした。前ストラット後セミトレーリングアームのサスペンション、ターボを備えるL20ET型を筆頭にツインプラグ化したZ系エンジンのラインナップ。
ところが発売から2カ月後となる10月、「4バルブなくしてDOHCは語れない」というキャッチフレーズとともにDOHCエンジンを搭載する2000RSが新発売されます。このDOHCはタクシー用の4気筒をベースに、プリンス系の開発者によりDOHCヘッドが与えられたエンジンです。
新開発FJ20E型で、実にケンメリGT-R以来、8年間途絶えていたDOHCの復活でした。しかし6気筒ではなく4気筒だったために「GT-R」と名乗ることが許されず、RS(レーシング・スポーツ)と命名されました。
このRSシリーズはトヨタがDOHCエンジンを存続させ、セリカの広告で「名ばかりのGTは道を開ける」と揶揄されたことへの復讐ともいえました。
3 「鉄仮面」の名前の由来

当初は自然吸気NAだったFJエンジンは1983年2月にターボを装備したFJ20ET型に発展します。150psだった最高出力は一気に190psへ増強され「史上最強のスカイライン」と銘打たれました。
同年8月のマイナーチェンジでは、RSシリーズにラジエターグリルがなく薄型ヘッドランプを採用する新しいスタイルが採用されます。この後期型RSを『鉄仮面』と呼ぶようになりました。
しかし、鉄仮面の愛称は発売されてすぐに付いたわけではありません。マイナーチェンジから2年後となる1985年8月、テレビドラマ『スケバン刑事』が放映を開始。
その続編『スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説』が1985年11月からスタート。この第二部で南野陽子演じる主人公、五代陽子は異様な鉄仮面を被って登場し、スケバン鉄仮面として認知されることになりました。
このドラマの影響から「鉄仮面」がスカイラインの愛称に転じます。
4 2000ターボインタークーラーRSへと進化

その後、RSシリーズは1984年2月に2000ターボインタークーラーRSと進化。インタークーラーを装備して205psまで出力を向上させます。
ライバルであるトヨタ・ソアラやセリカXXが2.8リッター6気筒だったことに対抗するためで、毎年のようにパワーアップを繰り返した歴史は、スカイライン史上でも例のないことでした。
5 6代目スカイラインが誕生するまで

スカイラインは鉄仮面と呼ばれる6代目誕生まで、実に5回ものモデルチェンジを繰り返しております。
1957年に初代であるL型/20系が誕生して以降、小型ファミリーセダンとして登場した2代目/S5型(1963年〜)、ハコスカの愛称でも親しまれる3代目/C10型(1968年〜)、ケンメリやヨンメリと呼ばれる4代目/C110型(1972年〜)と、スカイラインは短期間で何度もバージョンアップを繰り返してきた車種です。
その後5代目であるC210型が1977年に誕生し、鉄仮面と呼ばれる6代目スカイラインR30型が誕生します。なお、スカイラインは鉄仮面の登場以降も、13代目になるまでバージョンアップを繰り返します。
短期間で数多くのバージョンアップを経験しているスカイラインの中でも、2000ターボインタークーラーRSへと進化した鉄仮面は、多くの自動車好きにインパクトを与えたモデルといえるでしょう。
6 6代目スカイラインの走りをいつまでも

旧車市場を賑わす、鉄仮面と呼ばれる6代目スカイライン。実に13回のバージョンアップを繰り返すスカイラインの中でも、特にインパクトのあるバージョンアップを行った同車を所持するうえでは、維持費についての理解を深める必要があります。
6代目スカイラインを維持するのに年間でかかる費用の目安は、以下のとおりです。
| ガソリン代 | 約20万円 |
| 自動車税 | 約4〜5万円 |
| 任意保険 | 約3〜4万円 |
| メンテナンス費 | 約5万円 |
6代目スカイラインを維持するには、年間合計でおよそ40万円ほどかかるとみておきましょう。また、これらの金額に加え、2年ごとの車検費をあわせて用意しておく必要があります。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。