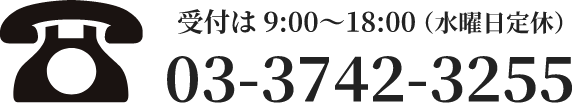2025年4月4日
歴代レガシィ|スバルの危機を救った名車が歩んだ36年を振り返る
富士重工業(現SUBARU)「レガシィ」は、北米市場での存在感を高めるために開発が進められ、1989年に初代がリリースされたモデルです。
その名称は「大いなる伝承」「受け継がれるもの」「遺産」などの意味を持つ英単語「Legacy」に由来します。
このネーミングには、スバルのテクノロジーと精神を将来に受け継いでいくという強い決意が込められており、スバル伝統の水平対向エンジを搭載しているのも特徴です。
実はレガシィが登場した1980年代後半、スバルは競合メーカーと比較して規模が小さく、独自路線を貫いていたこともあり、厳しい経営状況に直面していました。
当時のスバルの主力車種として位置づけられていたのが、レガシィの前身モデル「レオーネ」です。同モデルは国内外の小型車市場で思うような販売成績を上げられず、特に北米において他社の競合モデルに対して優位性を見出せない状況に陥っていました。
レガシィは、このような危機的状況を打開するために開発されたモデルです。
初代はセダンとワゴンの2つのボディタイプが用意され、中でもワゴンに関してはスバルの狙い通り、北米市場で高い人気を獲得し、ブランドイメージの向上や技術基盤の確立にも大きく貢献しました。
ところが2024年10月24日、スバルは2025年3月末でレガシィの受注を終了し、36年の歴史に幕を下ろすことを発表しました。
今回はスバルを倒産の危機から救った立役者として、日本車の歴史に足跡を残した名車「レガシィ」のこれまでの歩みを振り返ります。
目次
1 初代 BC/BF型

出典元: S.Candide / Shutterstock.com
1989年に登場した初代レガシィは、スバルの歴史を大きく変えるターニングポイントとなったモデルです。
開発プロジェクトの総括責任者を務めた中村孝雄氏の下、1966年の「スバル・1000」以来長年使われてきたプラットフォームを一新し、完全新設計で作り上げられました。
外観デザインは、くさび形をモチーフにしたスタイリッシュなボディラインにブリスターフェンダーを採用。各ピラーを黒色処理することで、ガラスが連続する航空機のキャノピーを連想させる斬新なデザインとなりました。
パワーユニットには、新開発の水冷水平対向4気筒エンジン EJ型を搭載。特にRSグレードに積まれたEJ20ターボエンジンは220馬力を発揮し、当時のクラス最高のパワーを誇りました。
さらに、全車に4バルブヘッドと電子制御インジェクションを採用し、クランク角センサー、カム角センサー、ノックセンサーからの信号をECUで学習管理する先進の電子制御点火方式も取り入れています。
駆動系では、FFと4WDを用意し、共に5速MTと4速ATが設定されました。
4WD-5速MT車にはセレクティブ4WDとフルタイム4WDがあり、RSとGTではリヤデフにビスカスカップリングLSDを装備。AT車には、前後輪のトルク配分を自動かつ無段階に変化させるアクティブ・トルク・スプリット4WD(ACT-4)を採用するなど、当時のスバルの4WD技術の結晶とも言える内容でした。
そんな初代レガシィの性能を語る上で欠かせないのが1989年1月21日、アメリカ・アリゾナ州フェニックスにて、リリース前のレガシィセダンRSが10万km耐久走行における走行平均速度223.345km/hという当時の国際記録を樹立した出来事。
燃料補給やメンテナンスなどのロスタイムを含む19日間で達成したこの記録は、レガシィの優れた耐久性と走行性能の証明となりました。
1991年6月にはマイナーチェンジで後期型へと進化。フロント周りが刷新され、新グレードのBrightonが追加。さらに、AT専用セッティングのEJ20Dと2.0L OHC EJ20Eエンジンが登場し、より細やかな燃料噴射制御が可能になり、操縦性や燃費が向上しています。
このように、当時のトップクラスと言える優れた性能を誇った初代レガシィは、1993年に販売が終了するまでに国内で累計26万8,367台が新車登録され、スバルを代表するモデルとしての地位を確立しました。
2 2代目 BD/BG型

1993年にリリースされた2代目レガシィは「継承・熟成」を開発テーマに、土屋孝夫氏が開発主査を務めたモデルです。
内外装のデザインには元メルセデス・ベンツのチーフデザイナー、オリビエ・ブーレイ氏がスバル社内スタッフと共に参加したことでも知られています。
当時の同格他社のモデルが3ナンバー化し、大排気量化の道を選んだ中、レガシィはあえて5ナンバーと2L以下の排気量を維持するという独自路線を選択。
この決断が功を奏し、5ナンバーながら上級クラスに負けない走行性能と室内空間を実現したことが高く評価され、2代目レガシィの商業的成功につながりました。
パワーユニットは、2.0LターボのEJ20Hが先代のEJ20Gから出力30馬力、トルク40Nmの大幅な性能向上を果たしました。
特筆すべきは、1996年6月のマイナーチェンジで登場し、ツーリングワゴンGT-BおよびセダンRSのMT車に搭載されたEJ20Rエンジンが、一般量産2.0L車としては世界初となる最高出力280馬力を達成したという点。
さらに、当時流行していたリーンバーンエンジンEJ20Nもラインナップされ、全エンジンの低フリクション化と効率向上が図られました。
四輪駆動システムでは、2.0LターボAT車にVTD-4WDを、それ以外のAT車にはアクティブ・トルク・スプリット4WD(ACT-4)を搭載。
2.0LターボMT車にはリヤにビスカスカップリングLSDを装備し、日本のFF車としては初のTCS(トラクションコントロールシステム)も用意されたのも特徴です。
パフォーマンス面では、1993年9月にアメリカ・ユタ州のボンネビルスピードウェイにて、デビュー前のツーリングワゴンGTが平均速度249.981km/hの世界最速ワゴン記録を樹立。その性能の高さを世界に示しました。
1996年6月のマイナーチェンジでは、大林眞悟氏らが中心となってシャシー、エンジン他全域にわたって大幅な改良を実施。
このマイナーチェンジでは、GT-BとRSのサスペンションには量産乗用車としては初のビルシュタイン社製倒立式ダンパーが採用され、ブレーキはフロントに16インチベンチレーテッド、リヤに15インチベンチレーテッドディスクブレーキが装備されました。
4WD全モデルに4センサー4チャンネルABSが標準装備されたのもポイントです。
中でもビルシュタイン社製ダンパーと280馬力のエンジンの組み合わせは大きな話題となりました。この成功により、GT-Bというグレード名は3代にわたって受け継がれることになります。
このような性能面での高い評価が後押しし、2代目レガシィは1998年に販売が終了するまでの期間で、国内累計49万5,471台が新車登録される大ヒットモデルとなりました。
3 3代目 BE/BH型

1998年6月にリリースされた3代目レガシィは「レガシィを極める」をテーマに、桂田勝氏が開発主査を務めたモデルです。
この3代目からは全グレードが4WD化され、FF車は廃止されました。また、2代目に引き続き5ナンバーサイズを維持したことも大きな特徴です。
ボディタイプはツーリングワゴン(BH型)とセダン(BE型)の2種類。
セダンはワゴンから半年遅れの1998年12月に発売され、新たにB4の名称が与えられました。B4はスポーティグレードのRSK、RSのみの設定とするなど、ツーリングワゴンとは明確な差別化が図られたのが特徴です。
この戦略は功を奏し、B4はスポーツセダン市場における代表車種として認識されるほどの成長を見せ、4代目以降にも引き継がれています。
当時は衝突安全性能が重要視される時代でしたが、3代目レガシィは自動車事故対策センター(現:独立行政法人自動車事故対策機構)が1998年と1999年に実施した衝突安全性能試験において、3.0L級の他社高級モデルを凌ぐAAAの成績を運転席、助手席共に唯一獲得し、その安全性の高さを証明しました。
パワーユニットは2代目から引き続き、EJ20型およびEJ25型水平対向エンジンを搭載。ターボモデルにも同様に2ステージツインターボが採用されました。
また、先代のグランドワゴンにあたるランカスター用に開発された3.0LのEZ30型水平対向6気筒エンジンが登場し、後にB4とワゴンにも採用されています。
EZ30型を搭載したB4のRS30は、富士重工業にとって初の大排気量セダンとなりました。
走行性能面ではリアサスペンションがマルチリンク式に変更され、ストラットタワーの張り出しをなくすことで、ラゲッジスペースの最大容量が先代よりも大幅に向上しました。
また、先代に引き続き上級グレードにはビルシュタイン製ダンパーが採用されたのもポイントです。
3代目レガシィが発売される直前の1998年4月には、アメリカ・コロラド州の公道での速度記録に挑戦し、1kmの区間平均速度で270.532km/hを達成。自らが持つ「ステーションワゴン多量生産車無改造部門」における世界速度記録を更新し、その高い性能を世に示しました。
優れた性能と安全性を兼ね備えた3代目レガシィは、2003年に販売が終了するまでの期間で国内累計25万6,849台が新車登録されました。
4 4代目 BL/BP型

2003年5月にリリースされた4代目レガシィは、清水一良氏がプロジェクトゼネラルマネージャーを務め、国際市場を強く意識して開発されたモデルです。
2003年11月には、富士重工製車種としては初めての日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したことでも知られています。
欧州市場への対応と衝突安全性能の向上を図るため、ボディを先代より35mm拡幅し、初めて3ナンバーへと進化しました。
この拡幅に伴い、3代目と比較して質感を増した内外装デザイン、ATの5速化などによってさらにプレミアム感の高いモデルへと進化しました。
また、4代目レガシィからは生産が日本とアメリカの2か国体制となり、国際的な展開が本格化しています。
特筆すべきは、ボディ剛性の向上と安全装備の充実を図りながらも、アルミニウムなどの軽量パーツや高張力鋼板を各所に導入し、従来型と比較してグレードによっては100kg近くの軽量化を達成した点。
3ナンバー化によって対衝突設計の自由度が高まったことが、この軽量化の実現に大きく寄与しました。
また、車体幅の増加により前輪の舵角が確保できるようになったことから、最小回転半径は先代の5.6mから5.4mへと縮小しています。
パワーユニットでは、これまで度々指摘されていたターボ切換え時の息付きやトルクの谷間といった問題を解消するべく、2代目と3代目で採用されていた2ステージツインターボを廃止し、初代以来のシングルターボに回帰しました。
採用されたツインスクロールターボは2,000rpmで290Nmを超える最大トルクを発生し、高回転仕様の水平対向エンジンとシングルターボの弱点を見事に克服。
さらに、ドライブ・バイ・ワイヤ機構「エレクトロニック・スロットル・チャンバー」の採用や、インプレッサSTIですでに使用されていた等長等爆エキゾーストマニホールドの採用により、水平対向エンジンの宿命とされてきた排気干渉を防ぎ、燃焼効率の向上を実現しました。
国際市場向けの展開も積極的に行われ、2006年にはドイツ向けを中心にLPGとのバイフューエル仕様「スバル・エコマチック」を投入。
2008年には量産車用としては世界初となる水平対向ディーゼルターボ仕様も欧州向けに発売されました。この2.0Lディーゼルエンジンは150馬力の最高出力と350Nmの最大トルクを発生し、EUのユーロ4排ガス規制に対応していました。
同年、パトカーとして警察車両では珍しいMT仕様のBL5 2.0GTが導入されたのも興味深い点です。高速道路交通警察隊用の交通取締向けとして6台が導入され、2021年時点でも山口県警が使用しています。
これまで、レガシィは過去3回のフルモデルチェンジを4〜5年間隔で行ってきましたが、この4代目はスバル初のミニバン「エクシーガ」の開発があったことや、高い完成度から安定した人気を保っていたことから、およそ6年にわたって販売が続けられ、歴代の中でも最長のモデルライフとなりました。
2009年に販売が終了するまでの期間で、4代目レガシィは国内累計28万8,889台が新車登録されました。
5 5代目 BM/BR型

出典元: Foto by M / Shutterstock.com
2009年5月にリリースされた5代目レガシィは、富士重工業執行役員・スバル商品企画本部長およびSTIの社長を兼任する日月丈志氏がプロジェクトゼネラルマネージャーを務めたモデルです。
生産は先代から引き続き、日本とアメリカの2ヶ国体制で行われました。
この5代目では北米市場からの要望に応え、先代と比較して車体を大幅に拡大。室内長・室内幅・室内高が広くなり、ゆとりある室内空間を確保。車体の大型化にあたっては、標準ボディを車幅1,780mmで設計し、北米仕様およびアウトバックはフェンダーの拡張で1,820mmとするという工夫が施されています。
一方で、大型化に伴い、重量は各グレードで4代目よりも約100kg増加しています。
室内設計では、インストルメントパネル右端に電動パーキングブレーキが装備されたことにより、従来のハンドレバーがなくなり、センターコンソールのレイアウトに余裕が生まれました。この電動パーキングブレーキは6速MTを含む全モデルで採用されています。
また、レオーネ以来受け継がれてきたサッシュレスドアが廃止され、一般的なサッシュ付きドアに変更されたことで、ドアの剛性向上と開口部の拡大につながりました。
ドアノブも4代目までのフラップ式からバーグリップ式に変更され、デザインはより現代的な印象となっています。
パワートレインでは、4代目から大型化が進み、2.0Lエンジンは廃止。代わりに2.5L水平対向4気筒SOHCエンジン、2.5L水平対向4気筒DOHCターボエンジン、そしてアウトバックのみに設定された3.6L水平対向6気筒DOHCエンジンの3種類となりました。
特筆すべき技術革新として、2.5LのSOHCエンジンには縦置きパワーユニットを搭載する量産四輪駆動車としては世界初となるチェーン式バリエーターを採用したCVT「リニアトロニック」を新たに設定。
これにより、オーバードライブ走行時の燃費向上や、パドルシフトの採用で0.1秒以下の素早い変速を実現しました。このモデルからはMTは2.5Lターボ車のみの設定となったのもポイントです。
安全性能においても高い評価を獲得し、2009年8月には米国IIHS(道路安全保険協会)によって、レガシィ(日本のレガシィB4)とアウトバック(日本のレガシィアウトバック)が「2009トップセーフティピック」に選定されました。前面衝突、側面衝突、ボディ構造での各項目において全て「優」の評価を獲得しています。
2009年10月には2009-2010日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞「Best Value」を、2010年4月には自動車アセスメントにおける衝突安全性調査でグランプリを受賞。これは、スバルとしては2007年度のインプレッサに次いで二度目のグランプリ受賞となりました。
5代目レガシィは、2009年に販売終了するまでの期間、国内では12万6,525台が販売されました。
6 6代目 BN/BS型

出典元: Walter Eric Sy / Shutterstock.com
2014年10月にリリースされ、2020年まで販売された6代目レガシィでは、車種構成に大きな変化が見られました。
日本仕様ではツーリングワゴンが廃止され、4ドアセダンのB4と、クロスオーバーSUVのレガシィアウトバックの2種類となりました。
ボディサイズは北米市場をより意識し、先代からさらに全長50mm、全幅60mmと大幅に拡大され、全高は5mm低くなりました。この変更によって、これまでよりもさらに流麗なシルエットを実現しています。
パワーユニットは大幅に整理され、日本仕様では水平対向4気筒2.5LのFB25のみの設定となり、それまで人気だった2.0LターボエンジンFA20は姿を消しました。
海外仕様では先代に引き続き水平対向6気筒3.6Lエンジン EZ36も設定されています。
FB25エンジンは名称こそ先代モデルと同じですが、約8割の部品を新設計した実質的な新型と言えるもので、吸排気系や燃焼系を中心に大幅な改良が施されています。
これにより実用域での扱いやすさや軽快な走りを維持しながら、燃費性能の向上を実現。
さらに、チェーンの駆動音やピストン、オルタネーターなどの作動音を低減して静粛性を高め、吸気音のチューニングによって心地よいエンジンサウンドも獲得しました。
最高出力は175PSとわずかに向上したのもポイントです。
CVTのリニアトロニックにも改良が施され、アクセル開度によって変速特性を切り替えるオートステップ変速制御や6速マニュアルモードのパドルシフトを採用。トランスミッション内部のフリクション低減により燃費性能を向上させ、ダイナミックダンパーの追加によって振動騒音も低減しています。
走行性能面では、ボディやサスペンション取り付け部の剛性を高めることで、サスペンション部がしなやかに動く質感の高い走りを実現。
サスペンションはスタビライザーの改良やショックアブソーバーの減衰特性の最適化が行われ、上級グレードのLimitedには新バルブの採用とフロントストラットシリンダ径拡大により、ダンパーのピストン速度域に応じた減衰特性の設定を実現したスタブレックス・ライドが採用されました。
これによりコーナリング時の安定性と快適な乗り心地の両立を果たしています。
ステアリングは小型・軽量・高出力性能のコントロールユニットを内蔵した電動パワーステアリングを採用。ブレーキも高応答性ブースターを採用したことにより、応答性とコントロール性が向上しています。
このような総合的な進化が高く評価され、2015年9月には、レガシィに採用されている運転支援システム「アイサイト」や、B4、アウトバックが2015年度グッドデザイン賞を受賞しました。
特にアイサイトは運転支援システムとして初の受賞となり、グッドデザイン賞特別賞候補にも選出されるという栄誉を獲得しています。
7 7代目 BW型/6代目アウトバック BT型

出典元: The Global Guy / Shutterstock.com
2019年にリリースされた7代目レガシィは北米市場に特化し、それ以外の地域では販売されないという、スバルの戦略的変化を象徴したモデルです。
そんな7代目レガシィでは、6代目と比較して全長が40mm延長され、スバルのグローバルプラットフォーム「SGP」を採用しています。
パワーユニットは一新され、2.5リットル直噴FB25Dエンジンと2.4リットル直噴ターボFA24Fエンジンが新たに採用されました。このエンジン刷新によって、燃費性能と走行性能の両立を図っています。
注目すべきは、2024年4月23日にスバルから発表された情報です。7代目レガシィは2025年春に生産終了を予定していることが公表され、36年にわたる歴史に幕を下ろすことになりました。
一方、日本市場では2021年10月に6代目アウトバック(BT型)の販売が開始。このモデルも7代目レガシィと同じくSGPを採用し、ボディ構造や基本設計は共通しています。
アウトバックのエンジンでは、FB25直噴エンジンに加え、FA24ターボが採用されています。
特筆すべきは日本向けのパワートレインで、歴代アウトバックの中でも最小排気量となる1.8リットル水平対向4気筒直噴ターボエンジン CB18が搭載されました。
このエンジンは低回転域から300Nmの高いトルクを発生させ、リーン燃焼を採用することでレギュラーガソリン仕様でありながら優れた経済性と力強い走りを両立しています。
トランスミッションのリニアトロニックも進化し、発進時の加速や高速巡航時の燃費性能向上を図るため変速比幅が拡大されました。また、8速マニュアルモードも搭載され、よりスポーティな走りにも対応できるようになっています。
レガシィが北米市場に特化し、日本ではアウトバックのみが販売されるという状況は、クロスオーバーSUVへの市場ニーズの移行を反映したものと言えるでしょう。
スバルを救った「レガシィ」36年の軌跡
2024年10月24日、スバルは2025年3月末を持って、レガシィアウトバック日本仕様の受注終了を発表しました。
これにより1989年に登場したレガシィは、その歴史に終止符を打つこととなります。
そんなレガシィは、80年代後半にスバルを倒産の危機から救っただけでなく、グローバルブランドとしての地位の確立に大きく貢献しました。まさにスバルを象徴するモデルと言えるでしょう。
ところが、近年では世間のSUV需要が高まり、多種多様なモデルが展開されています。
それが要因となり、スバルが得意とする「独自性」を維持できず、本来の良さが活かしきれていなかったのかもしれません。
さらに、スバルがグローバル戦略を推進していることも1つの要因と考えられます。
中でも北米は、スバルの自動車販売台数のおよそ7割を占める重要な市場です。
そして、環境問題が日常的に取り上げられるようになった現代は、多くの自動車メーカーがEVシフトを進めている状況。日本と比較すると、北米ではその傾向がより顕著です。
現状を踏まえると、スバルが国内モデルの整理を決断するのも無理はありません。
このようにさまざまな要因が重なったことにより、レガシィの販売は終了しました。しかしながら、数々の偉業を成し遂げてきたレガシィの「遺産」は、今後もスバル車に脈々と受け継がれていくことでしょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。