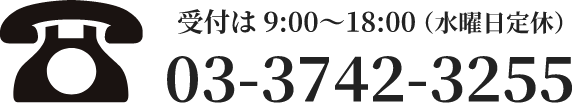2025年6月6日
マツダ ロードスター|世界で最も売れたの2シーター小型オープンスポーツのこれまで
マツダの2シーターオープンスポーツ「ロードスター」。
国内はもちろん、海外でも多くのファンに支持されてきたモデル。様々な自動車メーカーにも影響を与えたことでも知られています。
現在も高い人気を誇り、世界で最も生産された2シーターオープンカーとして君臨しています。また、その記録は伸び続けており、その勢いは止まることを知りません。
今回は、マツダが開発したロードスターについての軌跡を振り返ります。
目次
1 スポーツカー市場に影響を与えたロードスター

「人馬一体」のコンセプトのもと開発が行われ、1989年に誕生して以来、国内外のスポーツカー市場に影響を与え続けてきたマツダ ロードスター。
2000年には累計生産台数53万1,890台を達成し、世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカーとしてギネス認定を受けたことでも知られています。
2016年4月には、累計生産台数が100万台を突破し、日本のみならず世界的なベストセラーへと成長しました。
実はロードスターは、国内に先んじて北米市場で販売されたモデルです。日本では、北米でリリースした1989年5月から4ヶ月後の9月1日にリリースされました。
そして、ロードスターが誕生した1989年は、マツダの5チャンネル体制が開始した年でもあります。その中でも高級車を取り扱うユーノス店の第1弾モデルとして「ユーノス ロードスター」の名称で市場に投入されました。
そこから2025年までの約36年間、1996年にマツダの5チャンネル体制が終了後も継続して販売されているのはもちろん、発売初年度だけで国内9,307台、発売の翌年には世界9万3,626台を販売し、スポーツカーとしては驚くべき実績を残したのも特筆すべき点です。
ロードスターはライトウェイトスポーツ市場が冷え込んだ時代に登場し、人馬一体を体現した性能と必要最低限とも言える装備で、純粋な走る喜びを思い出させたモデルと言えるでしょう。
2 失われつつあったオープンスポーツカーの楽しさを蘇らせた「初代NA型」

2-1 初代ロードスターの概要
1989年9月に日本で販売が開始された初代ロードスターは、失われつつあったオープンスポーツカーの楽しさを現代に蘇らせた革新的なモデルでした。
田中 俊治氏、俣野 努氏、中島 美樹夫氏らによるプロダクトデザインと、開発主査の平井敏彦氏、後に引き継いだ貴島 孝雄氏のもとで開発が進められました。
ロードスター開発のきっかけとなったのは、マツダが北米に設立した「プラン・アンド・リサーチ スタジオ(後の Irvine R&D center)」で、スタッフが交わした「MGのようなライトウェイトカーがあれば」という会話がきっかけなんだとか。
その内容をもとに、当時「Mazda Research & Development of North America(MRA)」に在籍していた福田 成徳氏らによってデザインコンセプトが練られ、英国のインターナショナル・オートモーティブ・デザイン(I.A.D)社の協力のもと試作車が製作されました。
初代ロードスターはその卓越した走りと純粋なスポーツカー体験により、2004年に米国スポーツカー専門誌「スポーツカー・インターナショナル」のベスト・スポーツカー1990年代部門で第1位を獲得。
2004年には、スポーツカー・インターナショナル誌の「カー・オブ・ザ・センチュリー」でもベスト100に入るなど、世界的な評価を獲得した名車となりました。
2-2 随所に日本の伝統要素をモチーフに開発されたデザイン

初代ロードスターのデザインには、随所に日本の伝統要素が散りばめられているのが特徴です。
フロントマスクは能の小面、なだらかな起伏を持つサイドラインは能の若女の横顔、シート表面のパターンは畳のパターンをモチーフとし、リアコンビランプは江戸時代の両替商の分銅をデザインのモチーフにしています。
特徴的なドアハンドルには、運転前に茶室のくぐり戸から入る際のような緊張感を感じてほしいという開発者の思いが込められていたようです。
徹底した軽量化も特徴で、ボンネット、シリンダーヘッドカバー、PPFなどにアルミ材を積極採用。その結果、車重はMTモデルで940kg〜950kg、ATモデルで980kgという車両重量を実現しました。
軽量かつコンパクトなボディと適切なパワーバランスにより、まさに誰もが楽しめる走りを体現したモデルと言えるでしょう。
2-3 ロードスターの人馬一体を支えたパワートレイン

エンジンは、最高出力120ps/6500rpm、最大トルク14.0kgm/5500rpmを発揮し、高回転域での性能を重視したB6-ZE型1.6L直列4気筒DOHCエンジンを採用。
このエンジンはファミリアGTグレード搭載のB6型がベースになっており、縦置き化、VICSの非採用、レギュラーガソリン仕様化に伴う圧縮比低下などの変更が加えられました。
エンジンレイアウトは、重心を前輪車軸より後方に配置するフロントミッドシップを採用。
特筆すべき技術に「パワープラントフレーム(PPF)」があります。これはトランスミッションケースとリアデフケースをアルミ製フレームで直結する設計で、駆動系の剛性を高めてダイレクト感あるアクセルレスポンスとシフトフィールを実現。ロードスターの人馬一体を支える重要な要素として、初代から現行型まで進化しながら継承されている技術です。
サスペンションは当時のマツダ車では初となる前後ダブルウィッシュボーン式を採用。タイヤの接地面を有効に使い、直感的なハンドリングを実現しています。
シフト操作もストローク45mmと、当時の日本車では最小で、1990年3月には当初からある5速MTに加えて4速ATもラインナップされました。
1993年7月のマイナーチェンジでは、BP-ZE型1.8L直列4気筒DOHCエンジンへと排気量アップ。最高出力は130PS/6500rpm、最大トルクは16.0㎏m/4500rpmとなり、車体補強やLSDのトルセン化など様々な改良が施されました。
さらに1995年8月にはECUの16bit化やファイナルギアのローギヤード化など、さらに走行性能を高める改良が加えられています。
3 ロードスターの実力が海外にも認められた「2代目NB型」

3-1 2代目ロードスターの概要

1998年1月に登場した2代目からは「マツダ・ロードスター」の名称で統一され、マツダ店でも取り扱いがスタート。開発主査は初代から引き続き貴島 孝雄氏が担当し、チーフデザイナーには林 浩一氏が就任しました。
2000年のマイナーチェンジでは、外観を中心に刷新。フロントマスクとリアコンビランプが変更され、インテリアもシートデザインの変更やメーターパネルの刷新、インパネの一体感向上など、随所に改良が加えられました。
ボディ補強やパフォーマンスバーの追加により剛性も強化され、キーレスエントリーの導入など快適装備も充実。エンジンにはS-VTを搭載したBP-VE型1.8Lエンジンが搭載され、出力・トルクともに向上しました。
その後も衝突安全性の向上や排ガス規制対応に向けたマイナーチェンジが行われ、モデル末期の2003年には「ロードスタークーペ」と、限定モデルの「ロードスターターボ」も追加されました。
これらはマツダE&Tによる架装モデルで、ターボモデルはロードスター史上初の過給機付きエンジンでした。
2代目ロードスターの完成度の高さは国際的にも認められ、2003年8月には英国の権威ある自動車誌「AUTOCAR」の「Best Handling Car 2003」を受賞。
最終選考では、人馬一体のハンドリングが評価され、ポルシェ911 GT3を抑えて選ばれるという快挙を成し遂げました。
3-2 安全性と走行性能の向上を目指した設計

2代目からは、軽量化や空力性能の向上、対人衝突安全性の確保などの理由から、初代の代名詞とも言えるリトラクタブル・ヘッドライトが固定式ヘッドライトへと変更。
ボディサイズは、全幅が片側1.5mmずつの計3mm拡大されました。
走りを支えるエンジンは、先代の後期で廃止されたB6-ZE型1.6Lが復活し、改良型のBP-ZE型1.8Lと合わせて2種類をラインナップ。ATモデルには全車ABSが標準で装備されました。
2代目の開発では、サスペンション・ジオメトリーの見直しと補強の追加に加え、各部を徹底的に見直すことで重量増は1,000kgに収まる最小限に抑えられました。
バッテリーやスペアタイヤの位置も、低重心化の目的から初代よりも下方へ変更されるなど、走行性能の向上にも注力していたのもポイントです。
安全面では全車にエアバッグを標準装備し、先代のビニール製リアウィンドウはガラス製へと変更。オープン時の快適性も向上しています。
脱着式ハードトップは先代と共通設計とすることで互換性を確保し、幌はシート後方のトランク部とは別に収納されるため、オープン状態でも変わらない容量を確保するなど、使い勝手の向上も図られました。
4 基本プラットフォームを刷新し大きな転換を図った「3代目NC型」

4-1 3代目ロードスターの概要
2005年8月にデビューした3代目は、ロードスターの歴史においても大きな転換となったモデルです。開発主査は2代目から引き続き貴島 孝雄氏が担当し、チーフデザイナーには中牟田 泰氏が就任。
同年11月には、日本カー・オブ・ザ・イヤー2005-2006を受賞。マツダとしては、これが通算3度目の受賞となりました。
2006年、マツダはさらなる進化形として電動格納式ハードトップを搭載した「ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ(RHT)」を英国国際モーターショーにて出展。
開閉速度約12秒という世界最速クラスの動作と、ソフトトップモデルと同等のトランク容量を両立させた設計が評価され、日本で同年8月に発売されると大きな人気を博した一台です。
4-2 新開発プラットフォームを採用し刷新されたデザイン

最大の特徴は、初代から継承されてきた基本プラットフォームを完全に刷新したこと。
新開発のNCプラットフォームを採用し、基本をRX-8と共有しながらも設計の全面的な見直しを実施。この細部での徹底的な軽量化により、車両重量は1,100kgと、2代目の最終型との比較でわずか20kg増に抑えました。
全幅は5ナンバーの最大規格1,700mmを上回る1,720mmとなり、ロードスターとしては史上初の3ナンバー車となりました。デザインも一新され、2代目の立体的なフォルムから初代を思わせるフラットなデザインに回帰。サイドシルエットも先代のコークボトルシェイプから楕円状のオーバルシェイプへと変化しています。
外観は、張り出したフロントフェンダー、ドライバー保護の役割も果たすシートバックバー、2本出しのマフラーなどが特徴的です。
風の巻き込みを低減する可倒式メッシュ構造のエアロボードの採用や、Z字のように状に折りたたまれる「Zタイプ」と呼ばれるソフトトップなど、快適性と機能性を高める工夫も随所に施されています。
4-3 限られたスペースを有効活用されたインテリアと、本格的な走りを追求したパワートレイン

インテリアは初代を思わせる分割型デザインへと回帰し、ステアリングにはチルト機構が新たに追加されました。
サイドブレーキが運転席側に移設されたほか、シート後部には小型ストレージボックスを設置。トランクにはスペアタイヤの代わりにパンク修理キットを装備するなど、限られたスペースを有効活用する工夫も光ります。
走りを支えるパワートレインでは、従来のB型エンジンからアテンザやアクセラにも搭載される LF-VE型2.0Lへと変更。税制の関係から、欧州市場のみ1.8Lエンジンも設定されました。
トランスミッションは、グレードに応じて5速MT、6速MT、6速ATの3種類が用意され、特にスポーツグレードにはビルシュタイン製サスペンションや車体補強パーツが標準装備されるなど、本格的な走りを追求した仕様となっています。
5 原点回帰をテーマに開発された「4代目ND型」

出典元: Walter Eric Sy / Shutterstock.com
5-1 4代目ロードスターの概要
2015年5月にリリースされた4代目は、マツダの新世代技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」とデザインテーマ「魂動(こどう)-Soul of Motion」を全面採用した革新的なモデル。
開発主査は山本 修弘氏、チーフデザイナーは中山 雅氏が務めました。
4代目の開発では、初代への「原点回帰」が目標として掲げられ、軽量、コンパクト、FRという、初代以来のロードスターの本質に立ち返ることが目指されました。
グレード構成は当初、ベーシックなS、装備を充実させた「S Special Package」、最上位の「S Leather Package」の3種類。2015年9月にはサーキット走行も想定したモータースポーツ向けモデル「NR-A」が、10月にはRECARO社と共同開発したシートを採用した最上位スポーツグレード「RS」が追加されるなど、ラインナップが拡充されました。
2016年3月のニューヨークオートショーでは、「マツダ ロードスターRF(Retractable Fastback)」を発表。先代のリトラクタブルハードトップの後継モデルですが、スイッチ操作のみで電動格納式ルーフの開閉できるのがポイント。
ルーフラインがなだらかに傾斜するファストバックスタイルを採用したこのモデルは、約13秒で電動格納式ルーフを開閉可能です。
日本仕様では2Lソフトトップよりも排気量が大きく、最高出力158PS/6,000rpm、最大トルク20.4kgf・m/4,600rpmを誇る「SKYACTIV-G 2.0」を搭載。よりパワフルな走りを実現しました。
4代目ロードスターの洗練されたデザインも高く評価され、2016年12月の「オートカラーアウォード2016」では、ボディ色:マシーングレープレミアムメタリック×内装色:オーバーンの組み合わせがグランプリを受賞しました。
5-2 操作感と加速性能の両立を目指した設計
一貫した人馬一体の理念に基づき、エンジン、ボディ、サスペンションのすべてが最適化され、操作感と加速性能を両立しています。
フロントオーバーハングは短く抑えられ、人を中心に配置したコンパクトキャビンと組み合わせることで乗る人の姿が引き立つプロポーションを実現。スポーツカーらしい低くワイドな台形フォルムが存在感を際立たせています。
ボディ構造は先進の軽量化技術が惜しみなく投入され、アルミや高張力鋼板、超高張力鋼板の使用率を3代目の58%から71%にまで引き上げ。剛性を確保しながら大幅な軽量化を達成し、基本グレードの「S」は初代NA8C型と同等の990kgという軽さを実現しました。
日本仕様車では3代目から敢えてサイズダウンされた直噴1.5Lのガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」を採用。フロントミッドシップに搭載し、理想的な前後重量配分50:50を実現しています。
トランスミッションはMT車には、構造の見直しによって軽量化されたFR用の6速MT「SKYACTIV-MT」を、AT車には改良された6速ATを採用。AT車にはブリッピング機能や、ドライブセレクションなどスポーツドライビングをサポートする先進機能が装備されています。
安全技術面では「i-ACTIVSENSE」の導入により、ブラインドスポットモニタリングシステム(BSM)、車線逸脱警報システム(LDWS)、アダプティブフロントライティングシステム(AFS)など、様々な先進安全機能が搭載されました。2018年6月には、衝突被害軽減ブレーキも標準装備となり、安全性能が大幅に向上しています。
現代まで続くロードスターが持つ普遍的な魅力
初代NA型から現行ND型まで、常に人馬一体という変わらぬ理念のもと進化を続けてきたマツダ ロードスター。
時代とともに安全性能や環境性能が向上し、デザインの傾向は変わったとしても、ドライバーと車が一体となる走りの楽しさは決して失われていません。
ロードスターの魅力は単なる速さや性能数値だけではありません。その哲学が各世代の開発者たちの間で継承され、必要十分なパワーと軽量・コンパクトなボディによる絶妙なバランスを追求してきました。
オープンエアで風を感じる特別な体験、正確なステアリングフィールはドライバーを選ばず、誰もが走る喜びを感じられるスポーツカーとして世界中のファンから愛され続けているのです。
世界最多生産の2人乗りオープンスポーツカーとしてギネス記録を更新し続けるロードスターは、時代が変わっても色褪せない名車として、これからも多くのドライバーの心を掴み続けることでしょう。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。